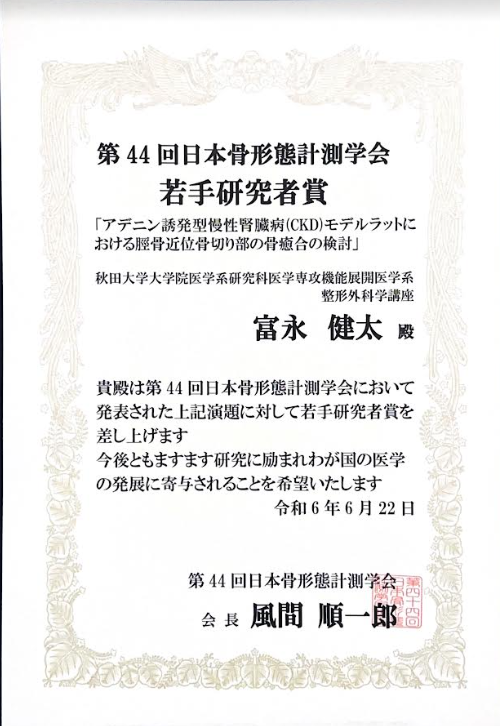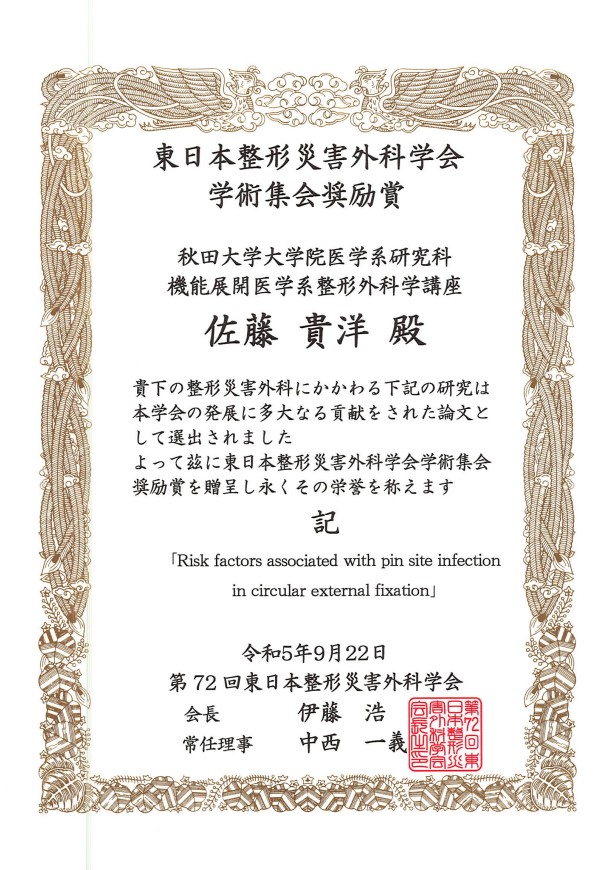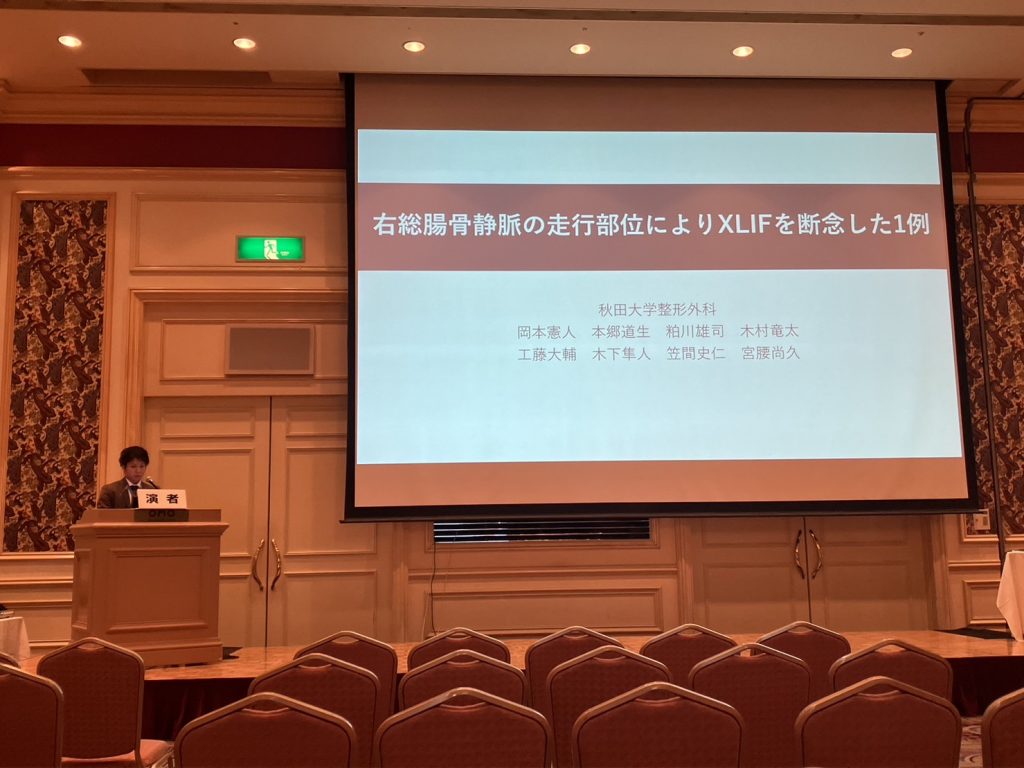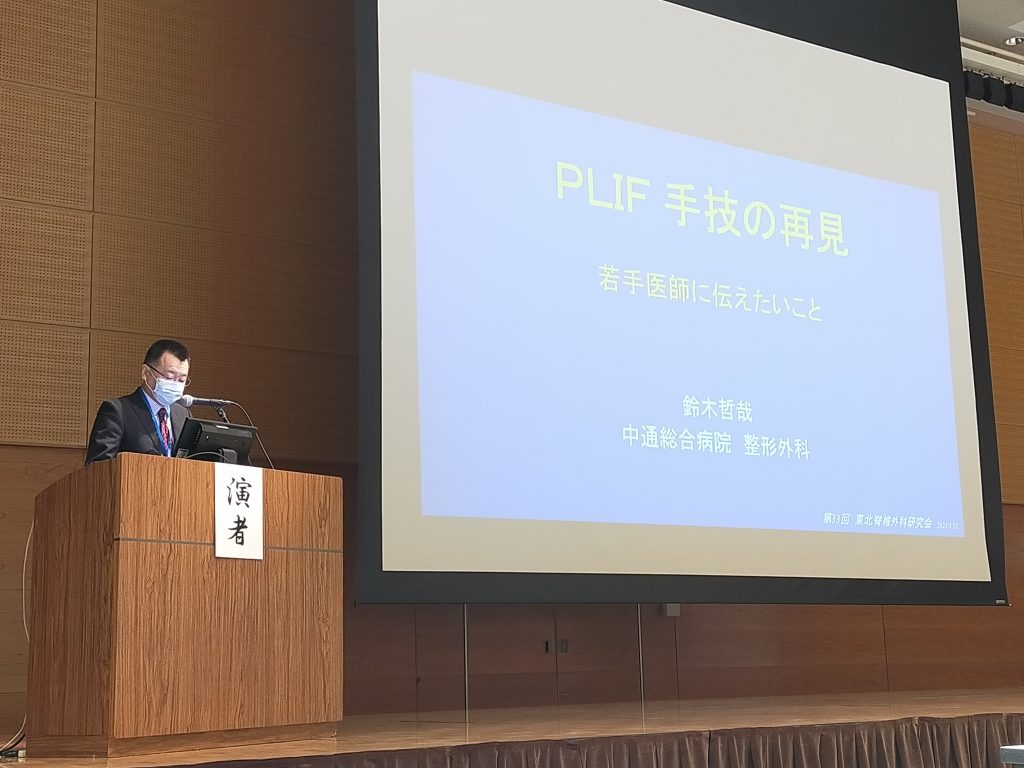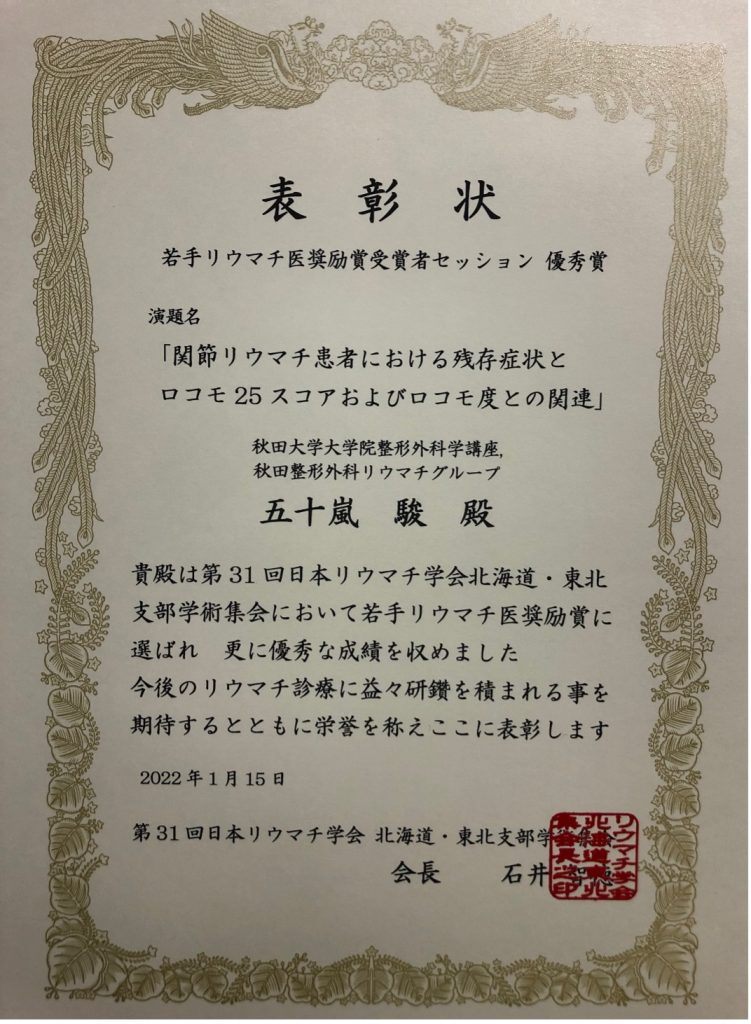2024年6月21日〜23日、福島県福島市コラッセふくしまで、福島県立医科大学 腎臓高血圧内科学講座、先端地域生活習慣病治療学講座 主任教授/運動器骨代謝学講座 教授・風間順一郎会長、福島県立医科大学 整形外科学講座 主任教授 松本嘉寛副会長、当講座教授の宮腰尚久副会長のもと、第44回日本骨形態計測学会が開催されました。
秋田大学からは全国最多7演題の発表があり、会長の風間教授からどの演題もとても素晴らしい発表だったとお褒めの言葉をいただきました。秋田大学の骨代謝研究の優れた実力を全国にアピールする大きな機会になったのではないかと思います。
今回私は学位論文のテーマである「アデニン誘発型慢性腎臓病(CKD)モデルラットにおける脛骨近位骨切り部の骨癒合の検討」という演題で発表し、幸運にも若手研究者賞をいただくことができました。これまでに当教室では粕川雄司准教授(ゴールドリボン賞)、野坂光司准教授(学会賞、ゴールドリボン賞、若手研究者賞)、藤井昌先生、赤川学先生、湯浅悠介先生が受賞されている賞とのことで身に余る光栄です。
CKDは続発性骨粗鬆症を引き起こし骨強度の低下や、骨折リスクの上昇をきたすことは明らかになっておりますが、骨癒合について検討したものはありませんでした。当教室でこれまでに多くの先生方が行っているラットの脛骨近位骨切りをCKDモデルラットに行い、骨切り後早期で骨癒合が遷延することが明らかとなりました。このような賞をいただくことができたのは宮腰尚久教授、粕川雄司准教授をはじめとする多くの先生方、研究室スタッフの御指導のおかげであると感じております。この場をお借りして深謝いたします。
今回は副賞として福島の郷土玩具である「赤べこ」をいただきました。
400年程前、会津地方に大地震が起こり、会津柳津円蔵寺虚空蔵堂が倒壊しました。その後、険しい崖の上に再建されることになり、木材運搬に使役された牛が険しい道のりのため数多く倒れましたが、最後まで働き通した牛が赤い色をしていたという言い伝えにあやかり、「忍耐強く壮健であれ」という願いを込めて張り子の赤ベコが作られるようになったとのことです。
大学院での実験・研究は時に忍耐強さを求められます。またこのような賞をいただけるように今後も赤べこに込められた不屈の精神で精進してまいります。引き続き御指導御鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。