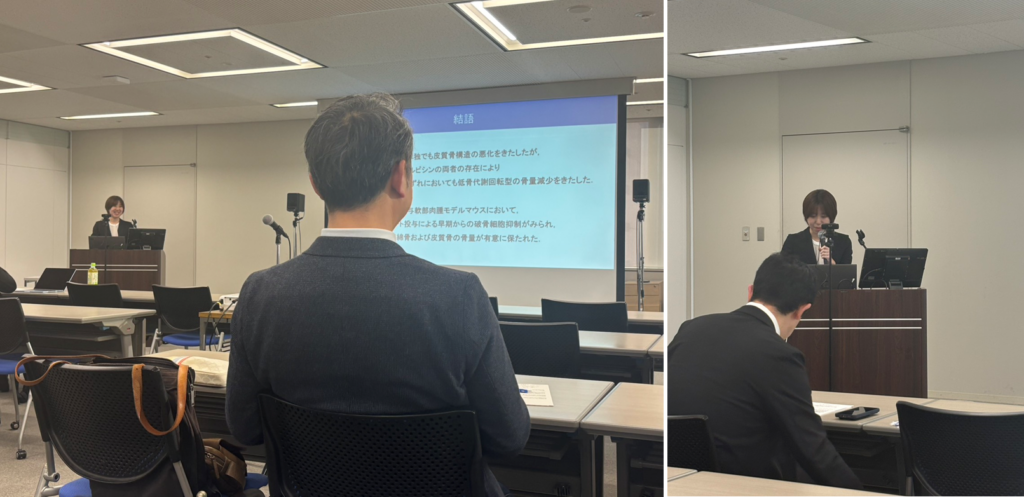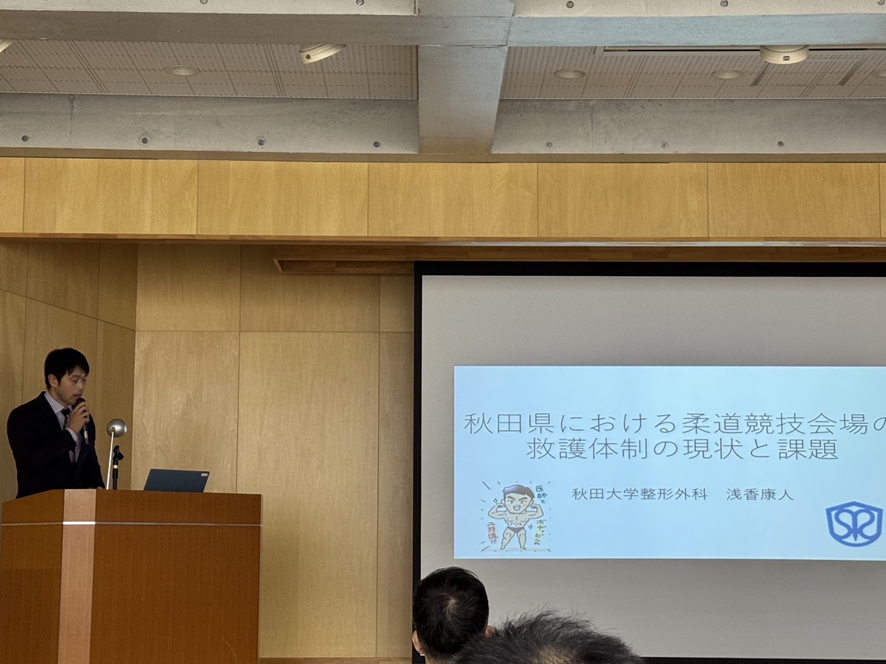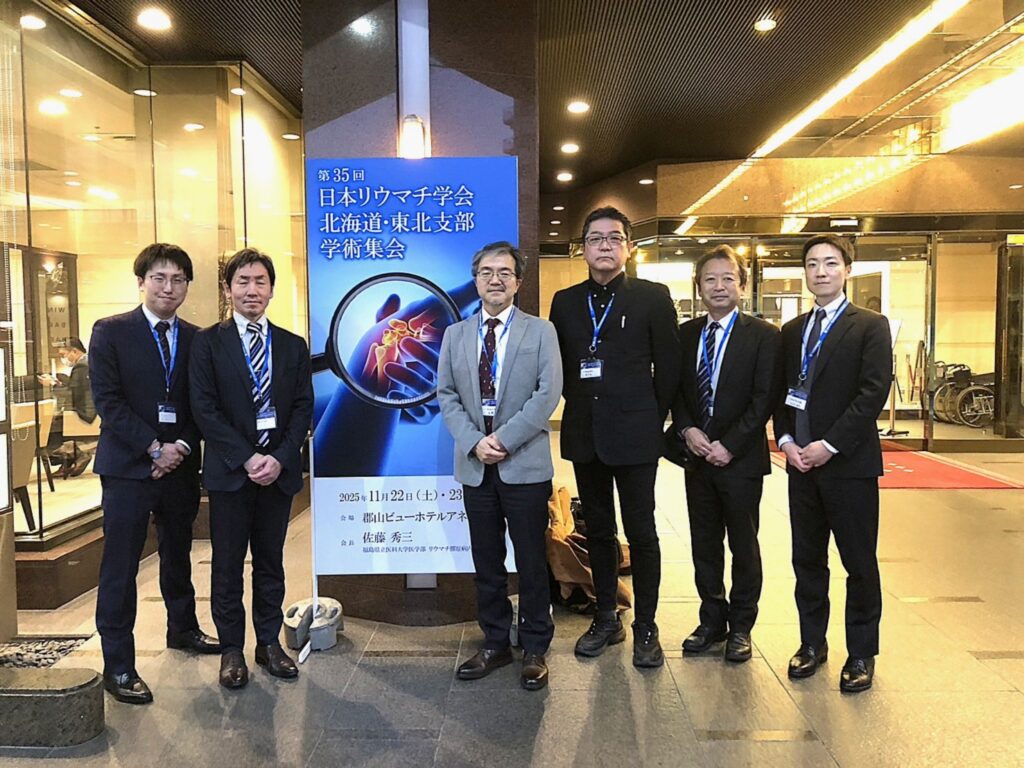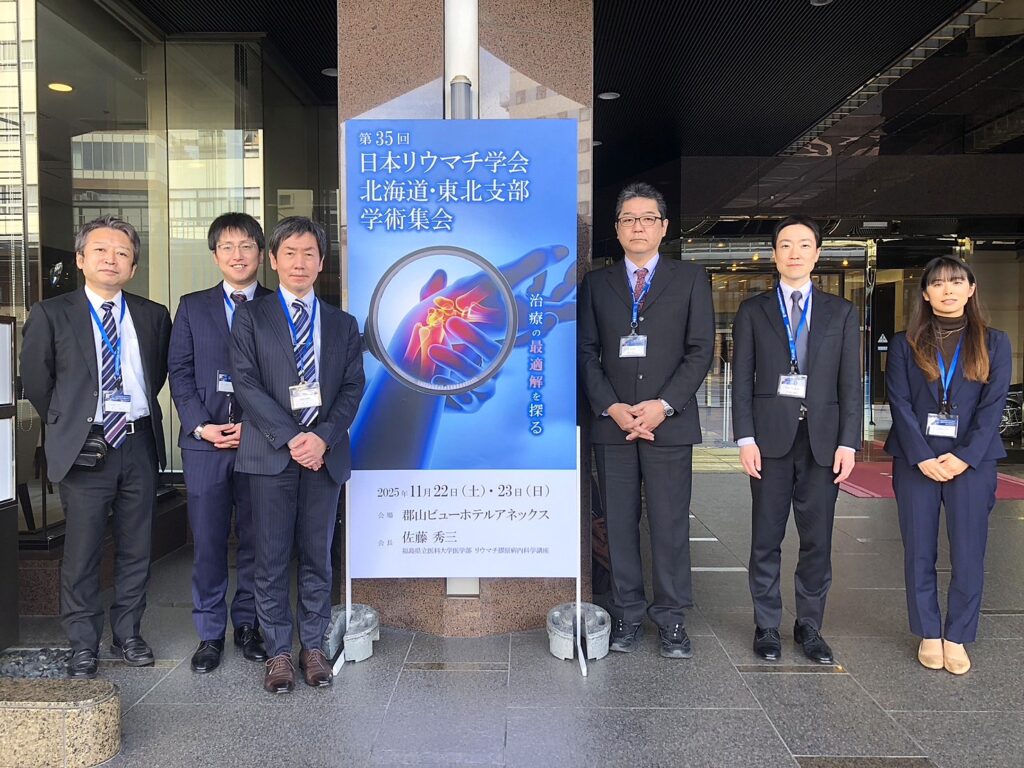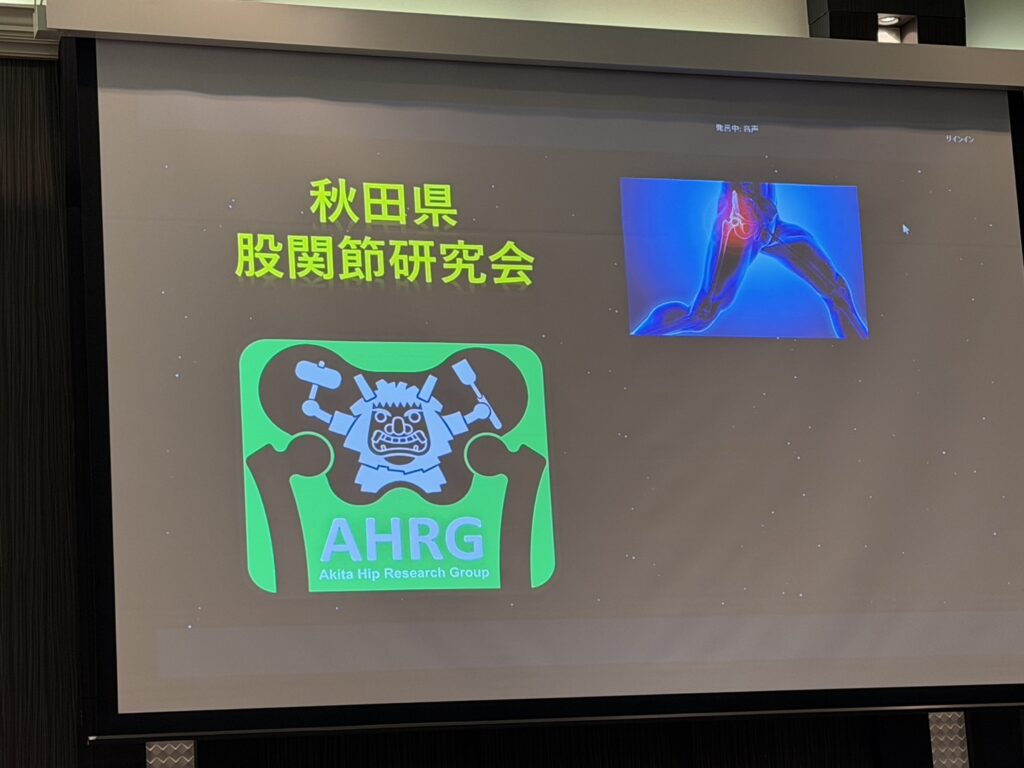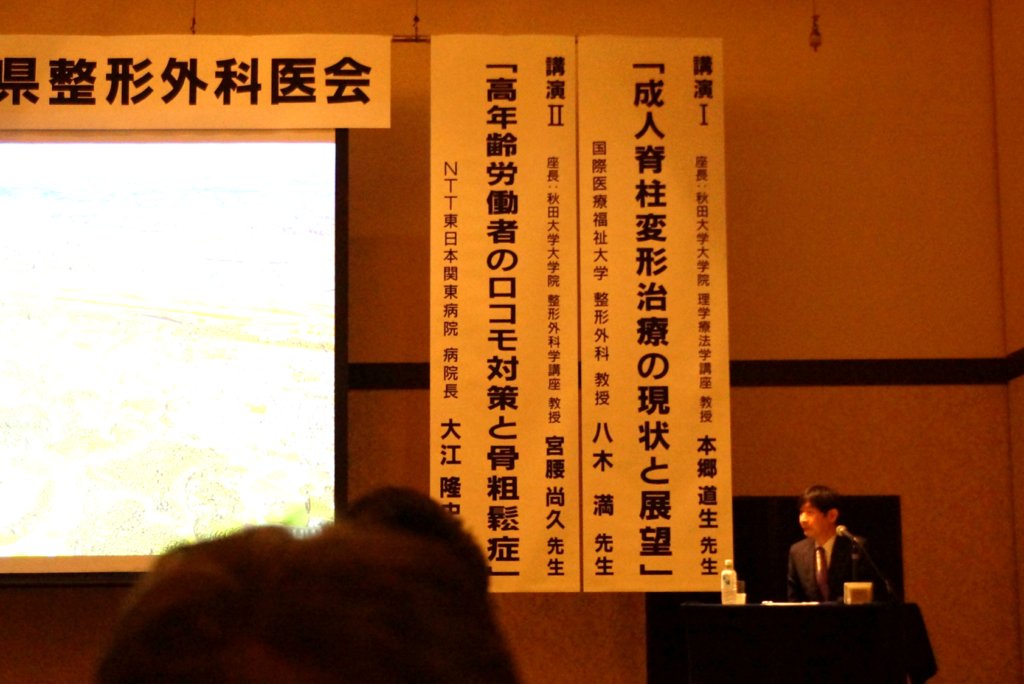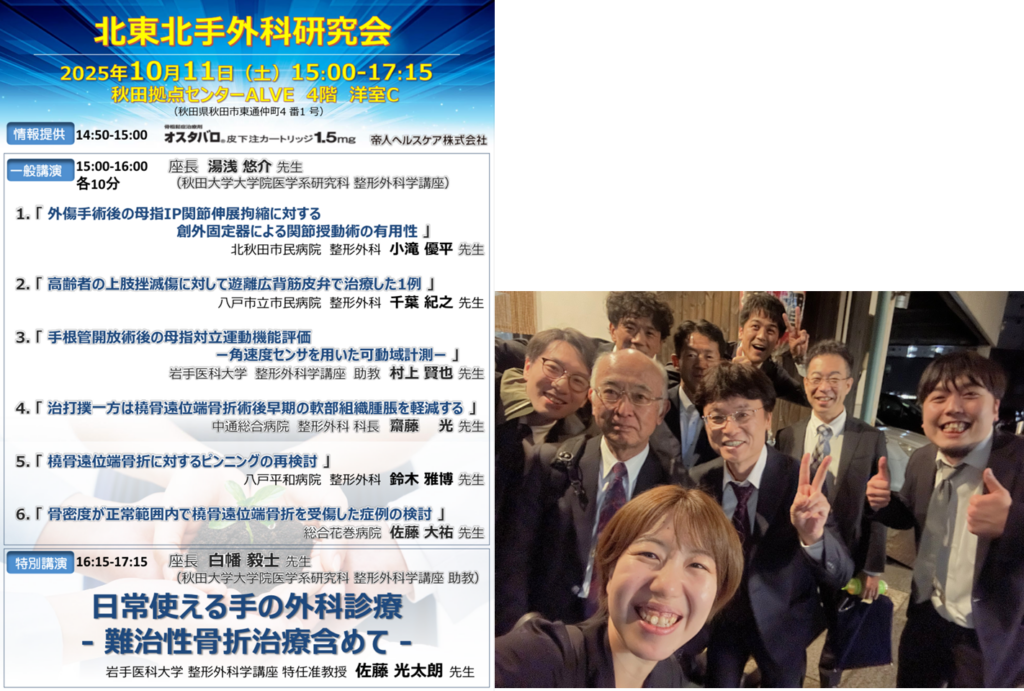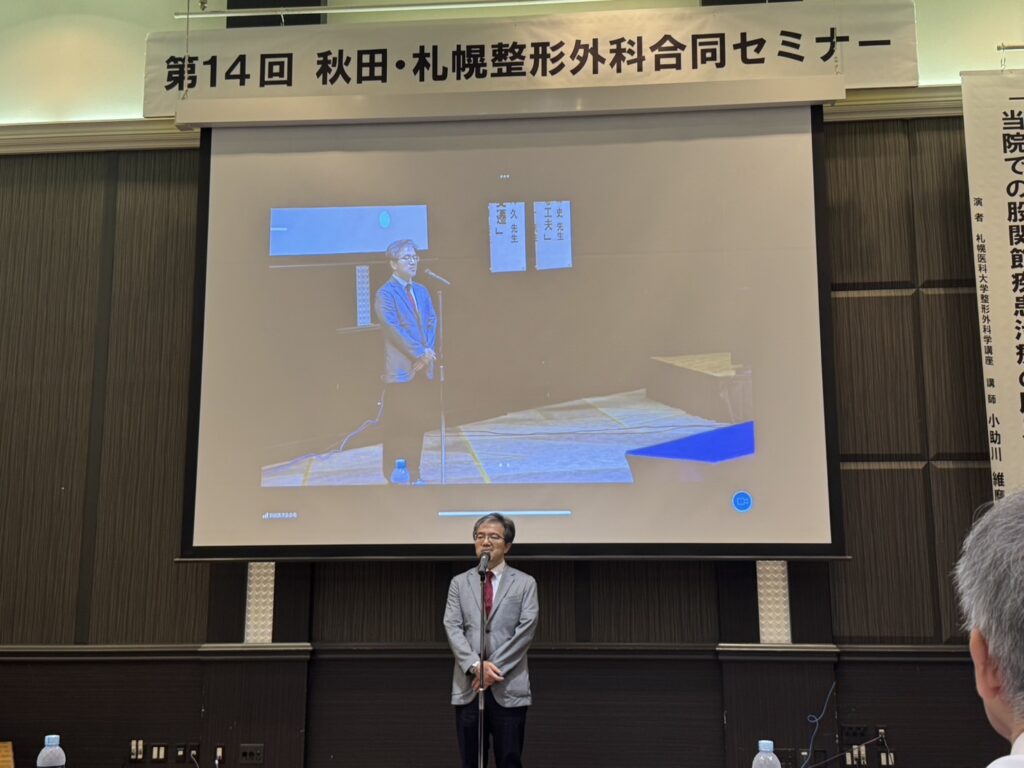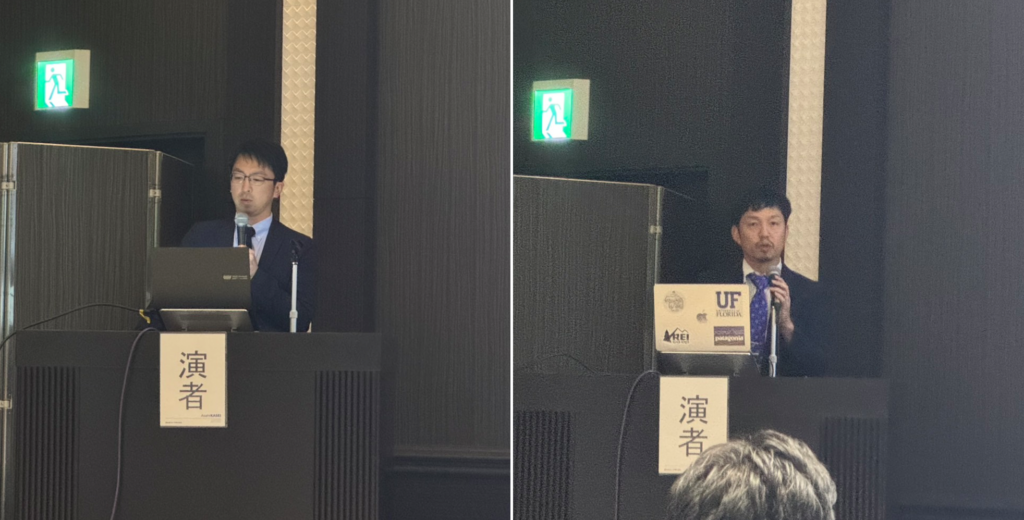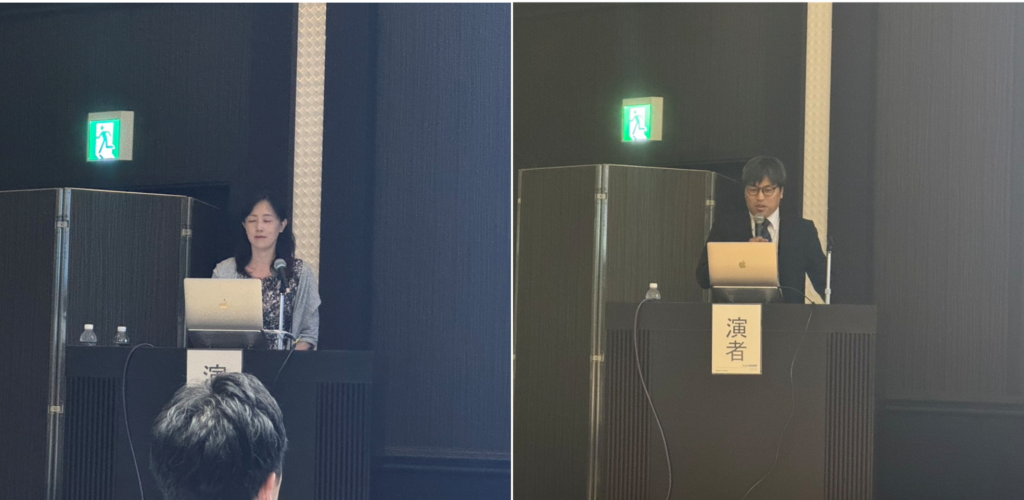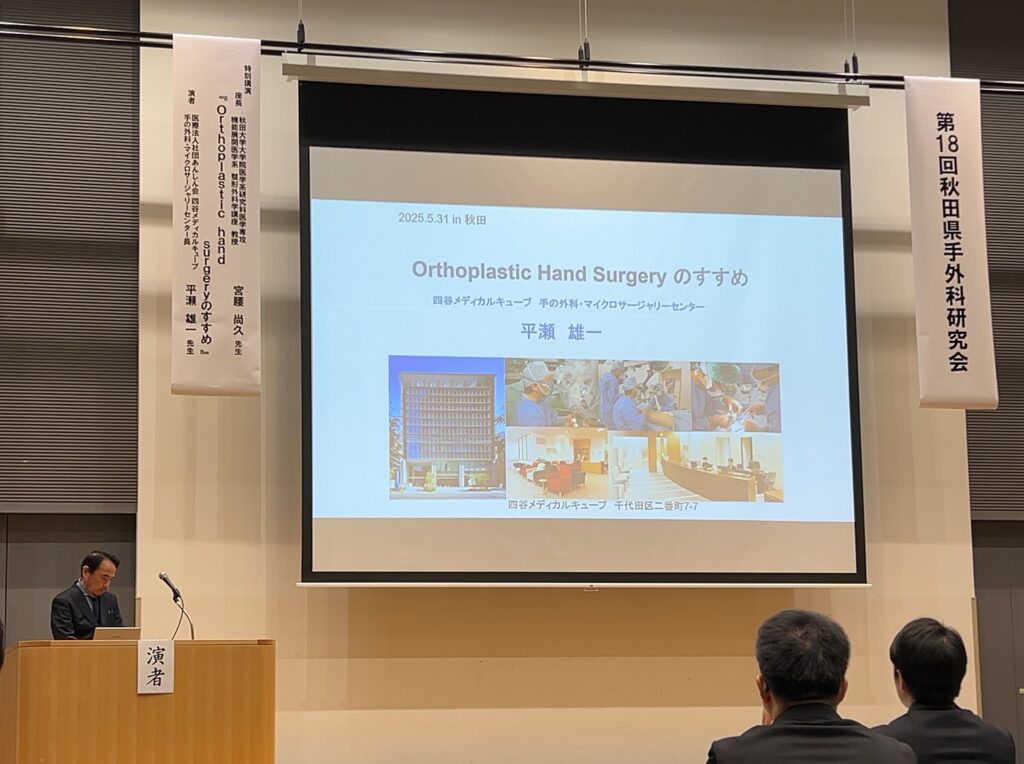2026年1月10日に、新宿パークタワーにて第26回OBMMG(Orthopaedics Bone and Mineral Metabolism Group)が行われました。今年のOBMMGは当学の宮腰教授が会長を務められ、骨代謝班の大学院生も多く参加しました。
一般演題は5題で、当学からは自分が基礎研究の発表をさせて頂きました。先行研究である笠間史仁先生の研究内容も併せて発表させて頂き、持ち時間20分は今までのどの学会よりも長く大変緊張しました。フロアの錚々たる先生方から厳しい質問が来るのではとヒヤヒヤしましたが、理路整然としたアドバイスやご指摘を頂き、自分自身大変勉強になりました。来月秋田にご講演に来て頂く防衛医大の堀内先生からは癌ロコモのタイプに絡めてモデルマウスの設定に関してご指摘を頂き、まさしくその通りだと感じました。今後の後輩たちの研究においても、モデルからしっかり考えなくてはならないと思いました。
ほかの一般演題は北里大、慈恵医大、産業医大、順天堂大からでしたが、どれもレベルが高く圧倒されました。順天堂大の山村先生がご発表されていたSIFKとOAの比較研究では、軟骨下骨やBML病変部位の微細構造から組織学的所見に至るまで詳細に評価されており、清書ではあまり見ることがない内容でしたので、大変勉強になりました。
特別講演では、「整形外科における次世代バイオマテリアルの展開:TiNbSn合金とOCP人工骨の研究と臨床応用」という題で東北大学の森優先生にご講演頂きました。従来のチタン合金の課題を見出し、高強度かつ低いヤング率(ただし熱で変化させることが出来る)を持つ金属として新たに開発し、ステムなどに応用されるとのお話でした。また、OCP人工骨に関してはゼラチンを用いることで扱いやすくなり、複雑な形状の骨欠損部でも隙間が埋まりやすくなるとのことで、とても良い材料と感じました。また、将来的には抗菌薬含有のスペーサーなどにも応用を考えており、化膿性脊椎炎や骨髄炎の治療もできればと仰っており、素晴らしい研究であると感じました。
情報交換会では、東都春日部病院の田中伸哉先生や長崎大の千葉恒先生をはじめレジェンドの先生方とお話をさせて頂き、たくさん刺激をもらいました。また機会があれば、今後もこの会に参加したいと感じました。
今後もリサーチマインドを忘れずに精進していきたいと思います。