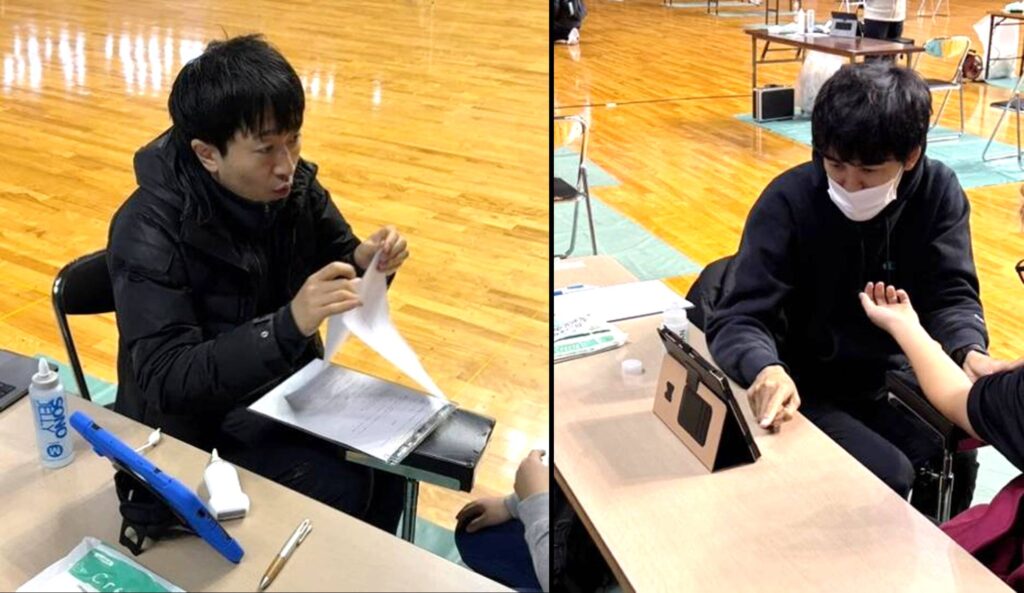ボルドーに来てから早いものでもう2ヶ月近くなりました。秋田はまだ雪が多いようですが、こちらは最高気温が15度を超えることもあるくらい暖かくなり、半袖で歩いている人もいるくらいです。秋田生まれ秋田育ちの私にとって、こんなに暖かい冬は初めてでとても新鮮です。
生活のリズムはだいぶ整い、クリニックでの手術の流れにも慣れてきました。リビジョンなどの難しい手術を見る機会も増え、また日本にはないインプラントなども知ることができ、日々新鮮な経験ができています。
先日ふと車の話になり、フランスではMT車が非常に多いと聞きました。MT車の方がコスト面で優れ、また地形や道路環境として山道や坂道が多いためエンジンブレーキが有効と考えられているそうです。フランスでの新車販売におけるMT車の割合は2017年で78%、近年はだいぶ減ったそうですがそれでも32%を占めるそうです(日本ではたった1%程度、Chat GPT調べ)。ヨーロッパ全体でも同じような傾向があるようで、特にレンタカーを借りる際には何も指定しないとMT車が出てくるそうです。(AT車は台数が少なく予約が必須だそう)。私は免許こそマニュアルで取りましたが、AT車しか運転したことがありません。せっかく国際免許を持ってきましたが、ボルドーは狭い道が多く、右側通行・左ハンドル、環状交差点、さらにMT車・・・運転のハードルは結構高めです。
もう一つ、フランスの面白い文化を知りました。先日仕事終わりに、「Baby footしに行こう!」と誘われ何のことかわからないままついていくと、バーにテーブルサッカーゲームがありました(写真参照)。フランスではカフェやバーだけでなく、学校や職場の休憩スペースなどにも設置されているそうで、国民的な遊びだということでした。その日はリーグ形式で試合が行われ、その場にいた人と即席タッグを組んでいきなり試合をしました。学生時代に遊びながらかなりの経験を積んでいた男性陣の中にはプロ級の腕前の人もいて相当に白熱した試合が繰り広げられていました。自分のチームはというと、全体の真ん中くらいの順位でしたが、慣れないながらも結構得点できたし、会話ほぼなし(私がフランス語あまり話せないため)でもそれなりのチームワークで親睦を深められました。気分転換にもコミュニケーションにもなる面白いゲームでした。職場の休憩室にもこういうのがあるというのはとても面白い文化だなと感じました。
文化の違いには驚くことや戸惑うこともありますが、新しい発見も多く本当に面白い毎日です。このような貴重な経験ができていることに改めて感謝し、また頑張っていきたいと思います。 à bientôt