先日開催されました、記念すべき第1回AKAS研究会におきまして、ASKAG youngersは、日常診療や手術の成果をまとめた発表をさせて頂きました。すべての演題で、質疑応答でも素晴らしい盛り上がりを見せ、非常に充実した内容であったと感じております。
私のテーマは、「大腿骨遠位骨切り術を安全に行うための大腿骨後面-膝窩動脈間距離の検討」というものでした。人工膝関節置換術で膝窩動脈損傷を経験したこともあり、対策や対応に関しては以前から興味がありました。題材を与えてくださった英知先生、いつもご指導ありがとうございます。
内容は、大腿骨遠位骨切り高位における、膝窩動脈と大腿骨後面との距離および大腿骨前後径を測定することで、骨切り時のボーンソーが動脈に接する可能性について検討したものでした。まとめると、レトラクターの保護、ボーンソーの取扱いおよび血管縫合の手技の習得が大事だという事です。私たちのような経験の少ない整形外科医だからこそ、今後トラブルシューティングの知恵と技を十分に身につけていこうと願って発表させて頂きました。拙い発表ではありましたが、ご評価頂きましたことに大変喜びを感じております。合併症対策や心得についてご教示頂きました島田教授には心より感謝申し上げます。また、“膝伸展屈曲で膝窩動脈距離に変化は見られない”という、貴重なご教示を頂きました安達先生におかれましても、この場をお借りしまして感謝申し上げます。
名誉ある第1回目の一般演題賞を頂戴しまして、身の引き締まる思いも致しました。勢いある若手がそろったグループで、同年代のメンバーと共に切磋琢磨していけたらと思っております。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、9月からは、ご講演賜りました岡村健司院長の下、羊ヶ丘病院で1ヵ月の研修生活を始めました。まだ3日目ではありますが、岡村院長直々に肩診療のいろはをご指導頂いたり、外傷の執刀させて頂いたり、今まであまり見る機会のなかった倉理事長の足関節鏡手術を拝見したりと、すでに充実度120%の研修を送っています。勉強不足なことが多々ではありますが少しでも爪痕を残し、秋田の勢いや意気込みを感じてもらえるように頑張っていきたいと、静かに思っています。
スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋…。存分に楽しんで秋田へ帰ります。
以上、秋の新札幌より、ご報告申し上げます。


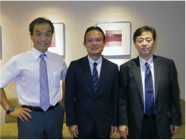 一般演題は、ASAKGメンバーがひとり一演題キャンペーンを張り、全員がレベルの高い発表をして頂きました。塚本泰朗先生(大森病院)、赤川学先生(大学病院)、杉村祐介先生(南秋田整形)、佐藤千恵先生(大学病院)、藤井昌先生(大学病院)、大内賢太郎先生(市立横手病院)、瀬川豊人先生(町立羽後病院)、佐々木香奈先生(中通総合病院)、冨手貴教先生(北秋田市民病院)、冨岡立先生(市立横手病院)の先生がたから素晴らしい発表を頂きました。また、ミニレクチャーでは、斉藤公男先生(市立角館総合病院)から最新の動作解析、歩行解析による臨床の疑問を裏付ける発表が行われました。われわれは、この動作解析に関しては、島田洋一教授のご専門でもあり、ASAKGでもそれを活かすべく、Motion analysis working groupを立ち上げました。そのリーダーである斉藤公男先生は、大学院の博士号もその動作解析で取得しており、今後の世界レベルでの活躍が期待されます。
一般演題は、ASAKGメンバーがひとり一演題キャンペーンを張り、全員がレベルの高い発表をして頂きました。塚本泰朗先生(大森病院)、赤川学先生(大学病院)、杉村祐介先生(南秋田整形)、佐藤千恵先生(大学病院)、藤井昌先生(大学病院)、大内賢太郎先生(市立横手病院)、瀬川豊人先生(町立羽後病院)、佐々木香奈先生(中通総合病院)、冨手貴教先生(北秋田市民病院)、冨岡立先生(市立横手病院)の先生がたから素晴らしい発表を頂きました。また、ミニレクチャーでは、斉藤公男先生(市立角館総合病院)から最新の動作解析、歩行解析による臨床の疑問を裏付ける発表が行われました。われわれは、この動作解析に関しては、島田洋一教授のご専門でもあり、ASAKGでもそれを活かすべく、Motion analysis working groupを立ち上げました。そのリーダーである斉藤公男先生は、大学院の博士号もその動作解析で取得しており、今後の世界レベルでの活躍が期待されます。 第1回AKASを無事、大盛況のうちに終わることができ、まずは一安心ですが、われわれは、若い組織ですので、Keep goingの精神で、謙虚に、一歩ずつ実践を重ねて参りたいと考えております。
第1回AKASを無事、大盛況のうちに終わることができ、まずは一安心ですが、われわれは、若い組織ですので、Keep goingの精神で、謙虚に、一歩ずつ実践を重ねて参りたいと考えております。







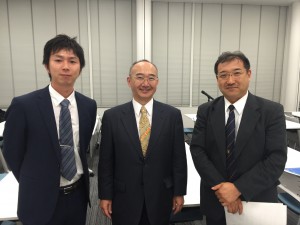


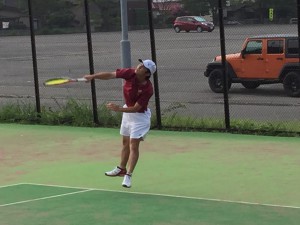
 2015/8/11、AM5:30ノーザンファルコンズ朝練習会が行われました。
2015/8/11、AM5:30ノーザンファルコンズ朝練習会が行われました。

