前回の留学だよりから気が付けば、はや2か月近く経ってしまった。この間にあった大きなイベントとしては、やはりビザ問題である。当初ビザなし(いわゆる観光ビザ)でイタリアに入国したため、90日以内にEU圏内から脱出しないといけず、9月末に日本に一時帰国。しかしながら苦労の末、学生ビザを入手する事ができ、すぐにイタリアに再入国する事ができたのであった。このイタリアのビザ事情、本当に入手は容易ではない。というか、ぶっちゃけResearchや研修目的ではもはやビザはとれないと思われる。これからイタリアに長期留学を考えているDrがいらっしゃったら少し考え直した方がいいかもしれない。ビザ入手までの戦いの記録は、留学記の最後に記そうかと思うので、ここでは詳細は割愛することに。
日本人が海外留学すると、食事が合わず日本食が恋しくなるとよく聞く。自分も日本に一時帰国する前は若干納豆やトマト味でない和風パスタなどの日本の味が恋しくなった。しかし今回一時帰国後、納豆ごはんを味どうらくとともにどんぶりで食べた後、翌日にはイタリアの食事が恋しくなってしまったのである。特にプロシュートクルード(生ハム)!留学前は家計節約のためトップバリューの生ハムをよく購入していたのだが、イタリアに来てからは現地の生ハムをほぼ毎日食べている。当初はスーパーで買ったものを食べていたが、最近はバルなどでワインとともに生ハム盛り合わせもしょっちゅう頼むようになった。とにかくイタリアの生ハムは安くてうまい。たまたま日本に一時帰国した際にスーパーでPARMAの生ハムが売っていたのだが、ちょっとの量で800円もしたのには驚いた。イタリアのスーパーだと、同じものが3倍くらいの量で4~5ユーロで変えてしまうのである。留学が終わった後やっていけるのかとても心配になった…。
イタリアの食事はチーズなど太りやすそうなイメージがあるのだが、日本に一時帰国した際に体重計に乗ると、3か月で5kgも痩せていた…。確かにズボンのベルトも2穴も変わったし、ジーンズがブカブカになってる気がする。手術でたちっぱなしの時間が多い事や、通勤で毎日計1時間歩くこともあるが、食事も大きく影響している気がする。日本にいるときは、ビール+おかずの後、締めのごはんで満腹になるまで食べていたのだが、こっちに来てからはビールまたはワイン+生ハム、チーズなどでつまむのが主体で、それで満足し、締めのごはんなどはそれほど食べていなかったかもしれない。塩分+アルコールの摂取量は極端に増えたが…。
今週で奈良医大の塚本先生が自分と同様にビザ取得のため、日本に一時帰国する事となった。塚本先生はまたしばらくしたら戻ってこられるが、奥様、2人のお子さんはビザが取得できず、3か月しないと再びイタリアに入国できないのである。何度か家族間で食事もし、お近づきになることができたので少し残念。このような機会があるのも留学の良い経験だと感じた。ここで食事風景の写真でも載せようと思ったのだが、いつもワインやビールを飲み、自分はいい気分になるためか写真を撮っておらず、食事写真が1枚も無い事に気が付いた…。今度は是非ご家族で秋田に遊びに来てください!その時は写真も撮りますので…。
※ハムつながりではあるが、今週末は家の近くのマッジョーレ広場で、年に1度のハム祭りが行われた。ボローニャのご当地ハムはMortadellaという、生ハムというよりは加工ハムみたいなやつである。広場では、たくさんの屋台がでており、Mortadellaのパニーニや焼きハム、ビール、ワインなどが食べれたり、ミスMortadellaみたいな女性が立っていたり、お持ち帰り用販売コーナーでは複数のハム業者が試食を出し、気に入ったものをカウンターで言えば、その場で大きな塊を切って売ってくれるというシステムである。通常ハムは薄切りで食べるので、受付で「Fetta? 」と聞かれ、当然スライスの意味かと思い、それでお願いしたら、結構な厚切りの状態でパックに入れられてしまった…。後で調べたら、Fettaは通常のスライス(日本的には厚切りか)で、Fettinaが薄切りのようである。それまでの客はみなFettinaだったのになんでうちらだけ…。イタリア語の難しさをまた実感したのであった…。

盛り合わせの1例。ワインがよく合う。

スーパーで買った安い生ハムとプチトマト。少し暗く映ってしまいおいしそうに見えないかもしれないが実際はうまいです。1パックにこの倍以上の量の生ハムが入って2.5ユーロ程。安すぎ。

マッジョーレ広場の会場、屋台が色々出てます。この日は最終日のため、もはや商品が無くなった屋台もあり、ちょっと寂しめ。

ハム販売エリア。たまたま人が少ない時に撮影したが、試食が出た時は人がうじゃうじゃとなり道が通れなくなる。

注文すると各業者のでかい塊ハムを取り出し、おじさんがその場でスライスしてくれる。レジに並んでいるときに、妻とともに奥のおじさんを見ていたら、笑顔でナイフを研ぐポーズをサービスしてくれた。やるぜ、おじさん。
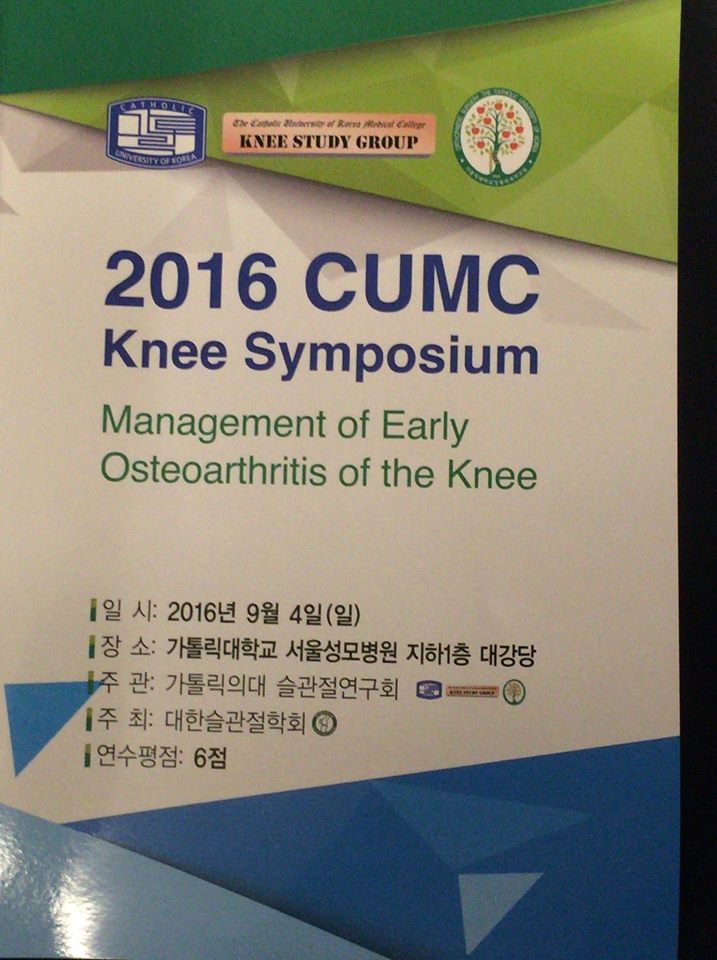


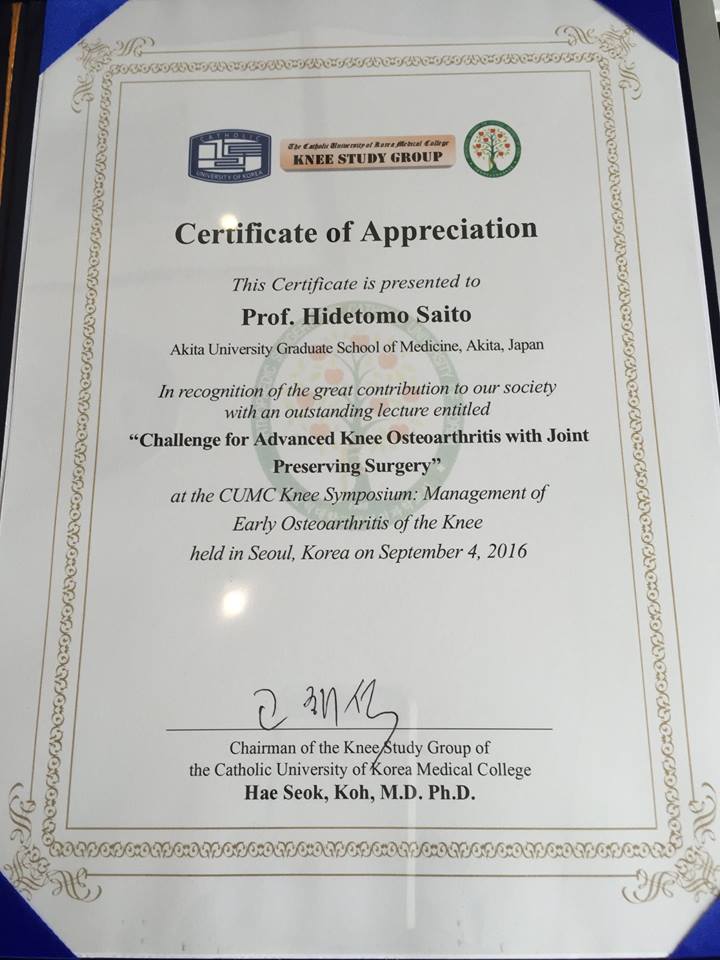






















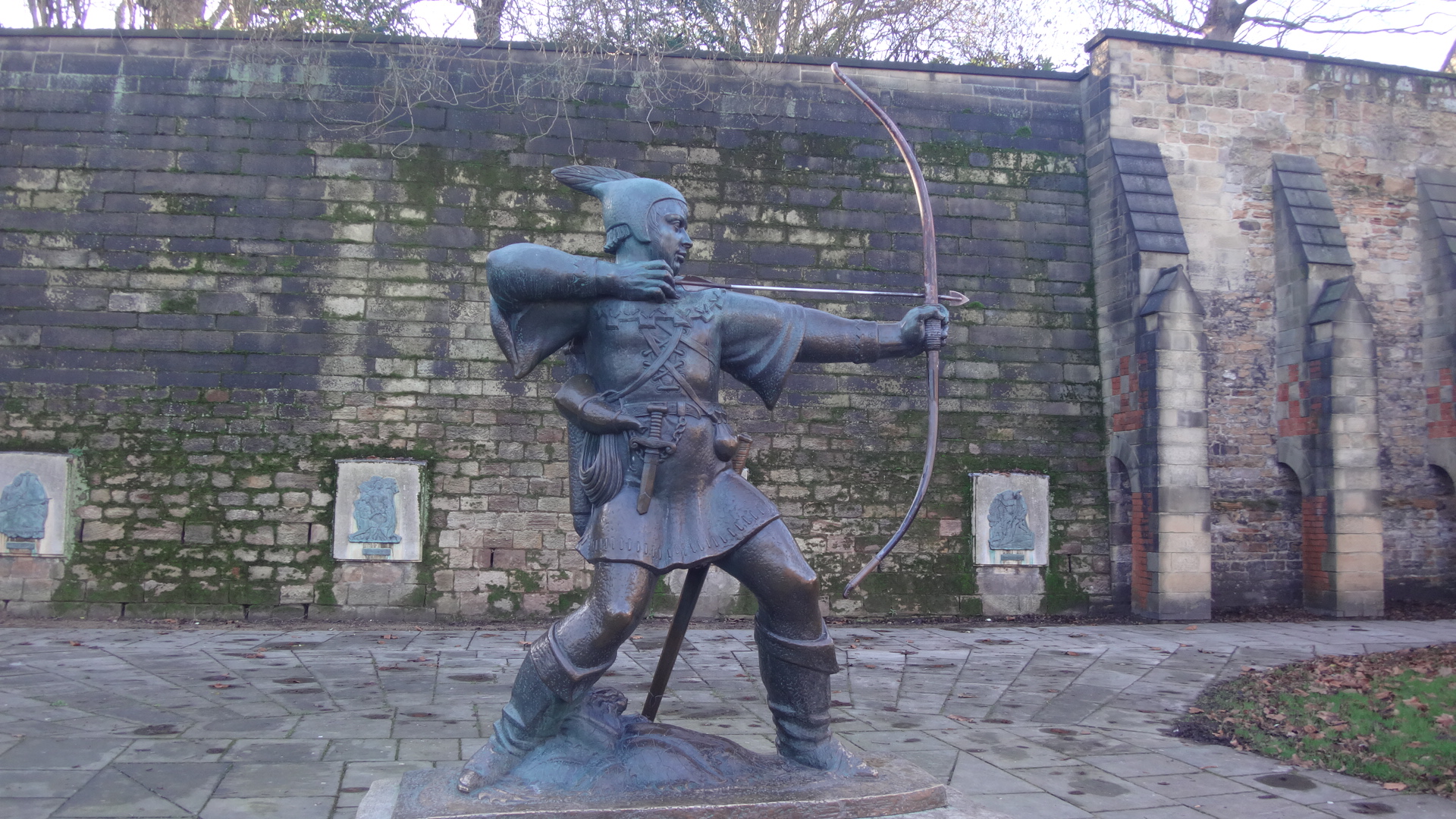


 先日テレビが欲しくなり、近くのホームセンターに買いに行った。英国でテレビを見るためにはTV licenceなるものを購入しないと見られないので(厳密には見られるが、ちゃんとお金を払わずにこっそり見ると罰金を請求される)、さっそくOnlineで購入した。しかし、残念ながら宿舎の電波が弱いためか?見られなかった。ブースターをつなげば映るかもしれなかったが、あいにくどこに売っているのか分からないし、日本の家電量販店のような店も近くにはない。仕方なく、届くか不安であったがAmazon.ukで注文してみた。結果は・・・ちゃんと届いたが、玄関先に荷物が置かれていた。
先日テレビが欲しくなり、近くのホームセンターに買いに行った。英国でテレビを見るためにはTV licenceなるものを購入しないと見られないので(厳密には見られるが、ちゃんとお金を払わずにこっそり見ると罰金を請求される)、さっそくOnlineで購入した。しかし、残念ながら宿舎の電波が弱いためか?見られなかった。ブースターをつなげば映るかもしれなかったが、あいにくどこに売っているのか分からないし、日本の家電量販店のような店も近くにはない。仕方なく、届くか不安であったがAmazon.ukで注文してみた。結果は・・・ちゃんと届いたが、玄関先に荷物が置かれていた。
