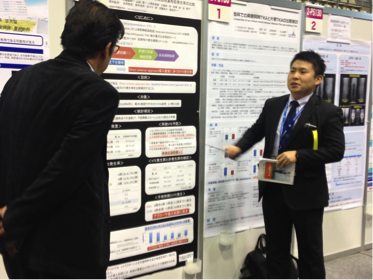2017年3月14日~3月18日,サンディエゴで開催されたAAOSで.口演してまいりました.発表内容は,足関節周辺骨折におけるMATILDA法(Multidirectional Ankle Traction using Ilizarov external fixator with Long rod and Distraction Arthroplasty of Pilon fracture )の有用性についてです.MATILDA法とは,秋田Ilizarov法グループで発案した,高齢者足関節周辺骨折に対して行うIlizarov創外固定の特徴を生かしたLigamentotaxisによる整復, Distraction Arthroplastyを行いつつの早期荷重を可能にするリング設置による治療法です(別冊整形外科66:173-177,2014,整形外科サージカルテクニック 5:56-62, 2015,整形外科手術 名人のknow-how イリザロフ創外固定を用いた難治骨折の治療.整・災外 59:1152-1157,2016).
20年後の関節症性変化が勝負とされるPilon骨折において,わずか1年の臨床成績のこの我々の後ろ向き研究に対し,これまで国内のプレゼンではときに批判も受けてきましたが,今回,難関のAAOSのOralに採択されたことで,さらに,フロアの反応も良好だったことで,我々のしてきたことが世界でも認められたと嬉しく思っております.
県内では,島田教授の応援に加え,山田晋講師が『MATILDAっていいな』と言ってくれたことがとても心強かったです.
また国内でも,私のIlizarovの師匠である大関教授や杉本先生,さらには多くのPilon骨折の達人の方たち,特にJSETS土田芳彦先生の応援は非常に心強く,『MATILDA法は世界に誇るべき優れた方法です』という励ましのメッセージを,AAOS発表前,緊張を和らげるために何度も読み返しました.今回創外固定学会で多くのシンポジウムを下さった白濱正博先生,また衣笠清人先生,野田知之先生,小川健一先生,松村福広先生ら,多くのプレートの達人,髄内釘の最上敦彦先生や,EOTSで認めて下さった黒住健人先生など,IlizarovなしでもPilonをラクラク治せてしまう天才外科医の方々の励まし,Ilizarov界では竹中信之先生の応援など,私が若い頃から本当に憧れ,目標にしてきた多くの偉大な先生方がMATILDA法を認識して下さったことはAIMGにとって本当にありがたいことです.
留学先のBossで,アメリカ足の外科学会の重鎮であるProf. Brodskyの高評価と激励も大変な自信になりました.
これまでIlizarovのプレゼンをするたびに,幾度となく『そんなもの(Ilizarovなんか)いらない』と言われてきました.その通りです.患者さんを,トラブルなく,内固定し,しっかり歩かせられて,早期に社会復帰させることができれば,あんな大きくて不快なIlizarovなどいらないのです.僕はMATILDA法が最強だ,などとは微塵も思っておりません.内固定で上手く,そして早く社会復帰させられたら,それに優るものはないのです.でも残念ながら,世の中は天才外科医だけではありません.私のもとには多くの悲惨な感染例が紹介されてきますし,骨はついたけど尖足で困るといった症例なども後を絶ちません.いい手術だけど2ヵ月ほど『足をつかないで』と言われてリハビリ病院で車イス生活になった人もいます(それはいい手術ではないかも).
いつも思うことは,プレート,髄内釘,Ilizarovは単なる固定材料であり,そこに優劣などつけるべきものではありません.Bone Transport,血管柄付腓骨移植,Masqueletも手術方法であり,それに優劣をつけようとするのも同様の行為と思います.大切なのは,どの治療戦略が,目の前の患者さんを最も上手く早く治すのかという,詳細な術前準備と,患者を最後までしっかり治そうとする強い意志(自分の哲学)と,自分の力量の把握だと思います.
何事も,我々の対象は患者さんです.外科医の手術自慢であってはなりません.その患者さんにとって何がベストなのか,症例ごとに大腿骨か下腿か,関節内か関節外かなどの部位,重症度のグレード,骨強度,若年か老年か,骨欠損なら大きさ,開放骨折ならGustiloのグレードなど,丁寧に適応を議論したり,エビデンスを模索すべきものなのに,一元的に何が一番いいかに固執することはナンセンスと思います.


 自戒も込めて,若手にはIlizarovは患者の快適さを犠牲にしているという謙虚さを常に忘れないように口を酸っぱく言います.1㎜の整復不良が,1日のLIPUSの注文忘れが,骨癒合を遅らせるのです.また,AFTTGの若手にはFlapは健常組織を犠牲にしているという謙虚さを忘れないMicrosurgeonになってほしいです(もちろん積極的に必要なFlapを行うことで,これまでのIlizarovよりも快適な術後生活を早く提供できる腕も身に着けてほしいです).相手は生きた患者なのです.
自戒も込めて,若手にはIlizarovは患者の快適さを犠牲にしているという謙虚さを常に忘れないように口を酸っぱく言います.1㎜の整復不良が,1日のLIPUSの注文忘れが,骨癒合を遅らせるのです.また,AFTTGの若手にはFlapは健常組織を犠牲にしているという謙虚さを忘れないMicrosurgeonになってほしいです(もちろん積極的に必要なFlapを行うことで,これまでのIlizarovよりも快適な術後生活を早く提供できる腕も身に着けてほしいです).相手は生きた患者なのです.
最近,偉大な先生方の講演を拝聴し,トラブルケースの相談を受け,思うところを綴ってみました.
日本中の優秀な外傷外科医が本気で力を合わせたら,日本中の患者がHappyになるはずです.いがみ合っている場合ではありません.
そのような日が一日も早く訪れるように,もう若手ではない自分は,『老害』と言われないように勉強を続け,もっともっと自分の尻を叩いて,奮起しなくてはと思います.時代は刻一刻と変わり,この多様性に適応するには,あらゆる分野の『融合』が必要なはずです.まさに『現状維持は退化』なのだと感じずにはいられない今日この頃です.







 Knee Group)を何卒よろしくお願い申し上げます。
Knee Group)を何卒よろしくお願い申し上げます。