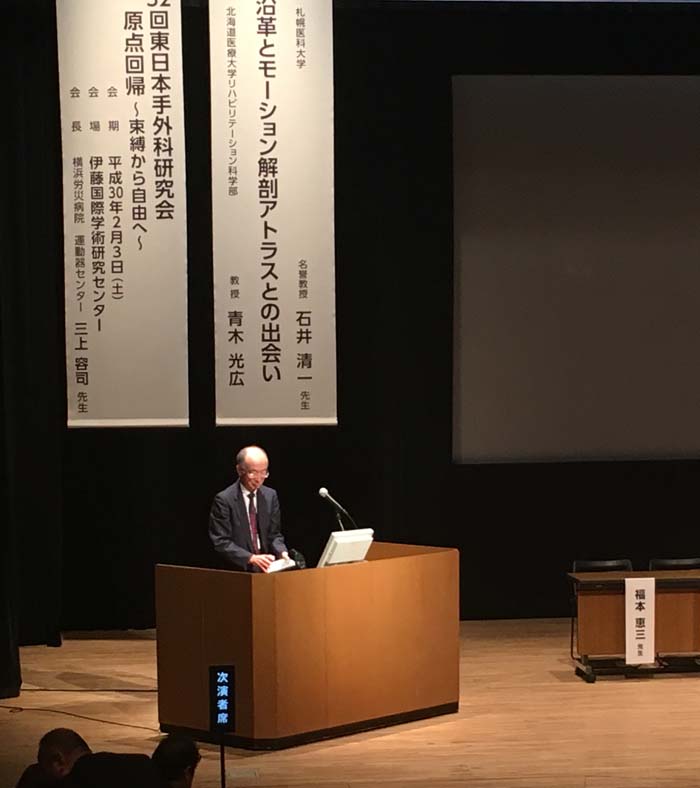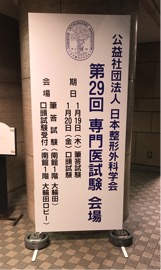2月18日(土)に秋田ビューホテルにて第14回秋田県骨軟部腫瘍セミナーが開催されました。
1演題目はイタリア留学から帰国された土江博幸先生による基調報告でした。土江先生からは、これまで当ブログで主にイタリアの文化についてご紹介頂いていましたが、今回は主に臨床的な内容でご発表いただきました。腫瘍に関しては積極的にアログラフトを用いたり、術後放射線療法を行うことが多く広範切除は日本に比べるとマージンが小さかったりなど、イタリアと日本との診療の違いについて提示していただきました。術中大声で歌いだすエピソードはさすが陽気なイタリア人、と感じました。
2演題目の教育講演は、『ビタミンD製剤による骨粗鬆症・運動器疾患の治療』というタイトルで秋田大学医学部附属病院の粕川雄司講師からご講演をいただきました。日常臨床でも身近になっているビタミンD製剤について、働きや代謝など基礎的な内容から説明していただきました。特に最近重要となっている慢性腎不全が原因となる骨代謝異常、CKD-MBDについての概念から診断、治療方針の建て方など臨床データを交えて詳しく解説していただきました。骨密度と骨代謝マーカーだけを見ていれば見落としがちですが、診断が重要な疾患であるだけに大変参考になりました。また、今回は骨軟部腫瘍セミナーということで腫瘍性の骨軟化症、FGF-23関連低P血症についてもご発表頂きました。
3演題目は東邦大学整形外科主任教授の土谷一晃先生の特別講演で、『外来診療に役立つ骨軟部腫瘍の知識 〜cancer survivorの骨粗鬆症対策を含めて』というタイトルでご講演をいただきました。現在は患肢温存が原則となってきた骨軟部肉腫治療の時代的背景からお話し頂きました。骨軟部腫瘍専門医、病理医でも診断が別れた症例を提示して頂き、臨床所見、現病歴、病理組織診断など総合的な診断が必要となるとお話され、骨軟部腫瘍の難しさを改めて感じました。また、生検などのために前医によって無計画に皮膚切開を置き、その後に行われる広範切除の侵襲が大きくなる事が問題となるunplanned excisionや、ガングリオンと誤診されて播種してしまった悪性腫瘍の症例、若年者でスポーツ外傷と誤診され発見が遅れるsports tumorという概念などご説明頂き、今後自分の外来診療でも十分に気をつけなければいけないと感じました。