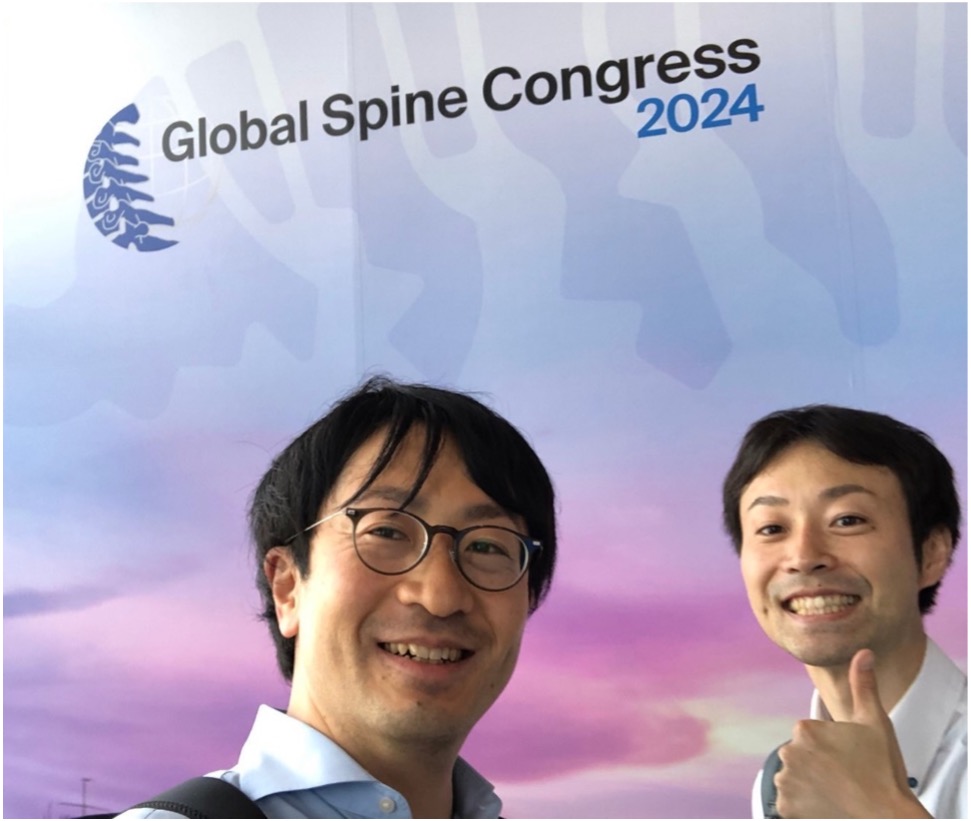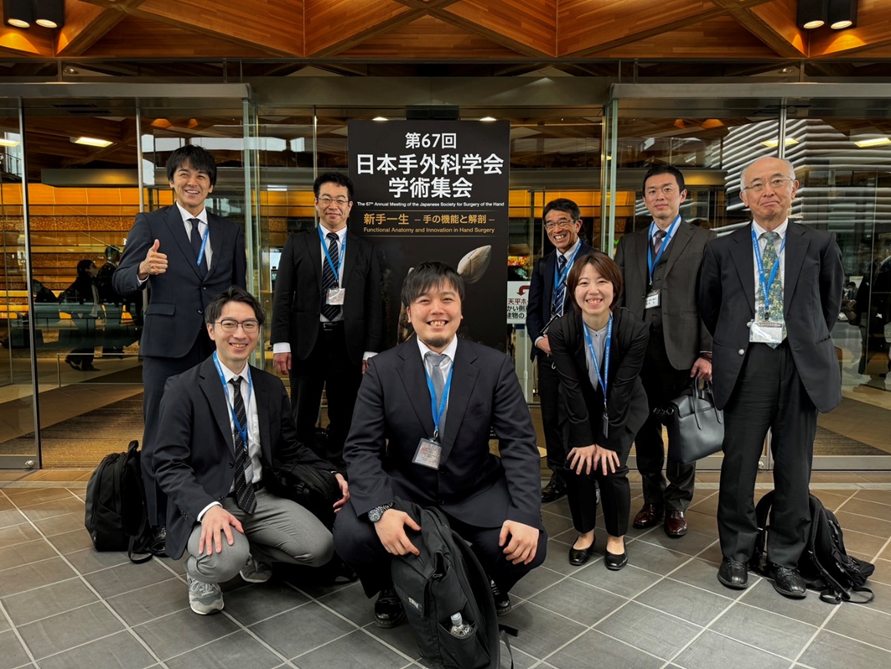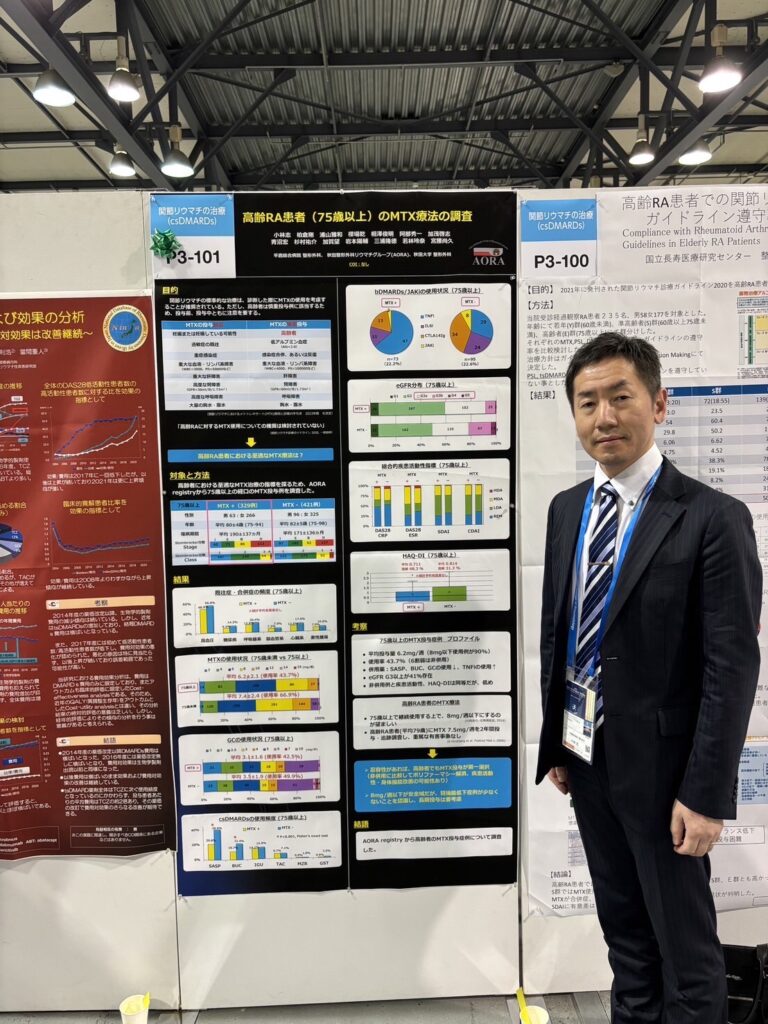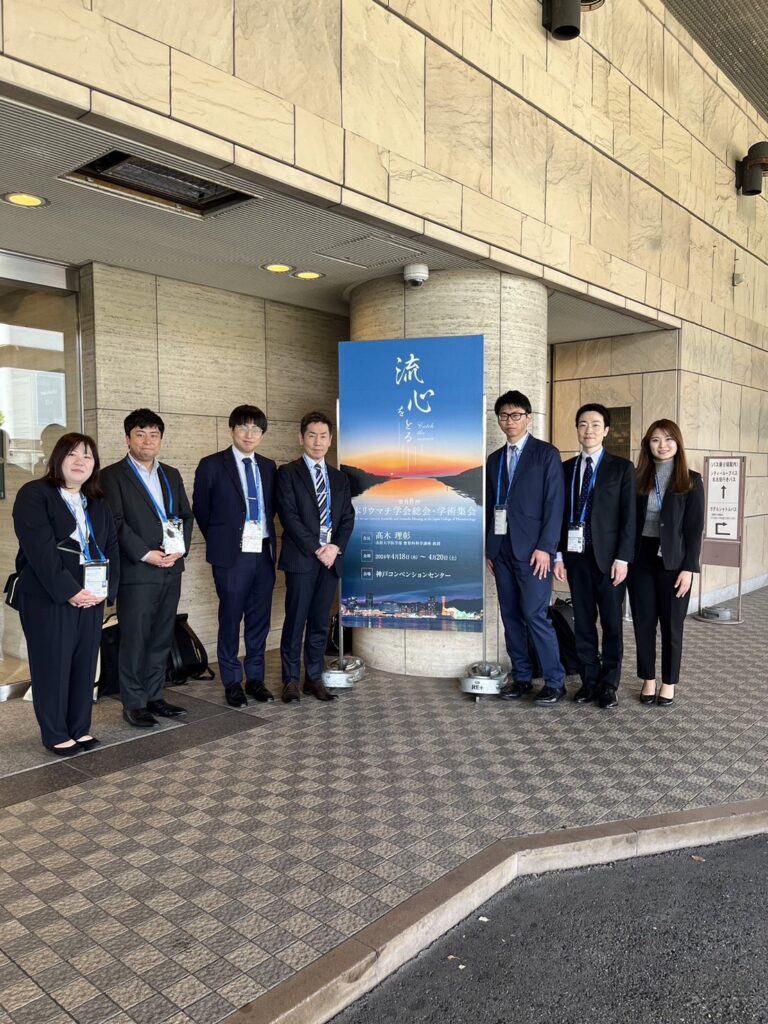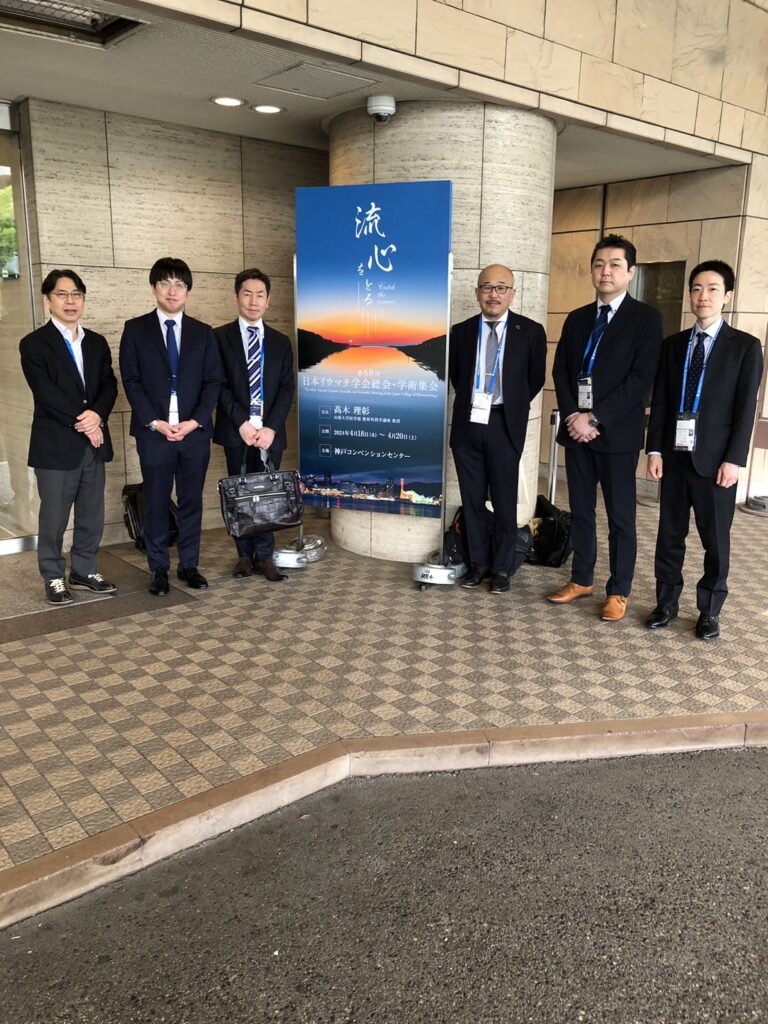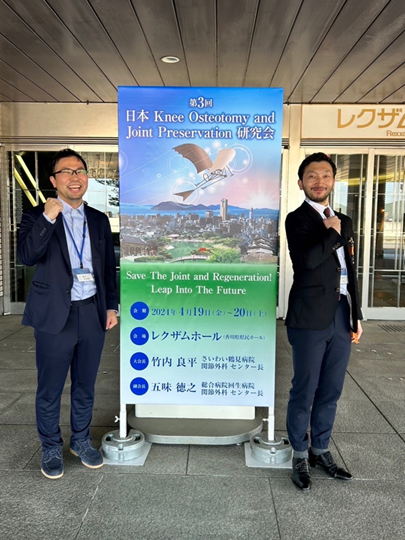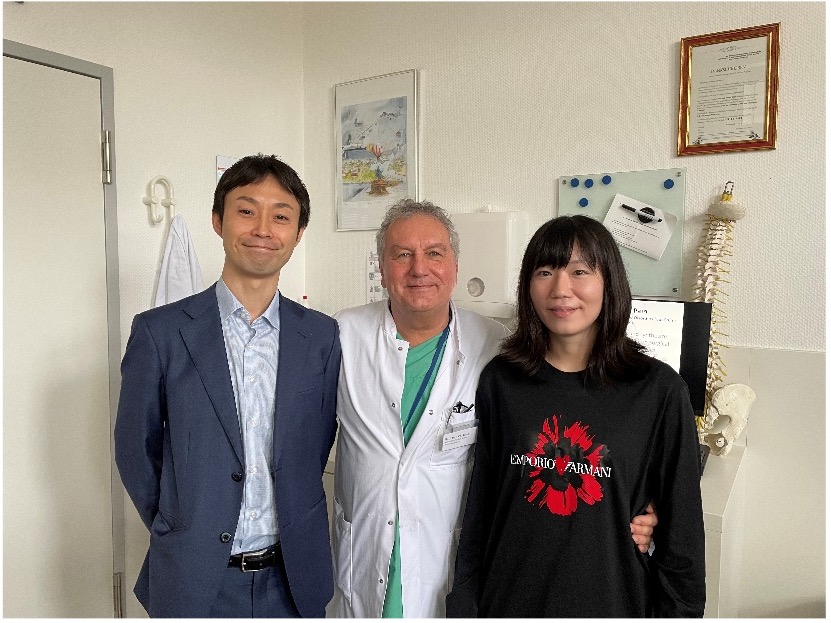2024年5月23日〜26日に福岡国際会議場で第97回日本整形外科学会学術総会(慶應義塾大学整形外科 松本守雄会長)が行われました。当教室からは56演題と多くの演題が採択され、各分野の先生方のご活躍が光る会となりました。
初日には菜なで同門会が開催され、久々に多くの同門が集い、大盛況の会でした。コロナ世代の私は、同門会の経験が少なく、普段なかなかお会いする機会がない上級医の先生方と一緒に水炊きを囲みながら、お話ができて貴重な時間でした。また、本学会に4人の研修医の先生が参加してくれました。4人とも整形外科に強く興味を持ってくれており、今後の秋田大学整形外科の発展が期待されます。最近は女性も整形外科に興味を持ってくれる後輩が増え、嬉しい限りです。一緒に整祐会を盛り上げていく仲間を増やすべく、引き続き勧誘活動にも力を入れていきたいと思います。
学会では、宮腰教授のシンポジウムを始め、先輩方の発表やランチョンセミナーを聞き勉強させて頂きました。私は3日目のポスター発表でしたが、緊張してしまい上手く話せず、まだまだ経験が必要と感じ、今後のモチベーションに繋がりました。ご指導頂きました先生方、本当にありがとうございました。
今回、親善スポーツ大会はバスケが中止となり、当教室からの参加はありませんでした。大会がなくともバイソンズは練習に励んでおり、先生方のバスケ愛を感じました。来年、再来年こそは全競技大会が復活し、スポーツの場でも先生方の勇姿が見られることを願っております。
来年は東京で開催予定となっています。本教室からさらに多くの演題が採択され、東京の地に集い切磋琢磨できると良いと思います。3年目の連続採択を目指して、私も日々精進してまいります。

学会会場前に集うと一大勢力でした
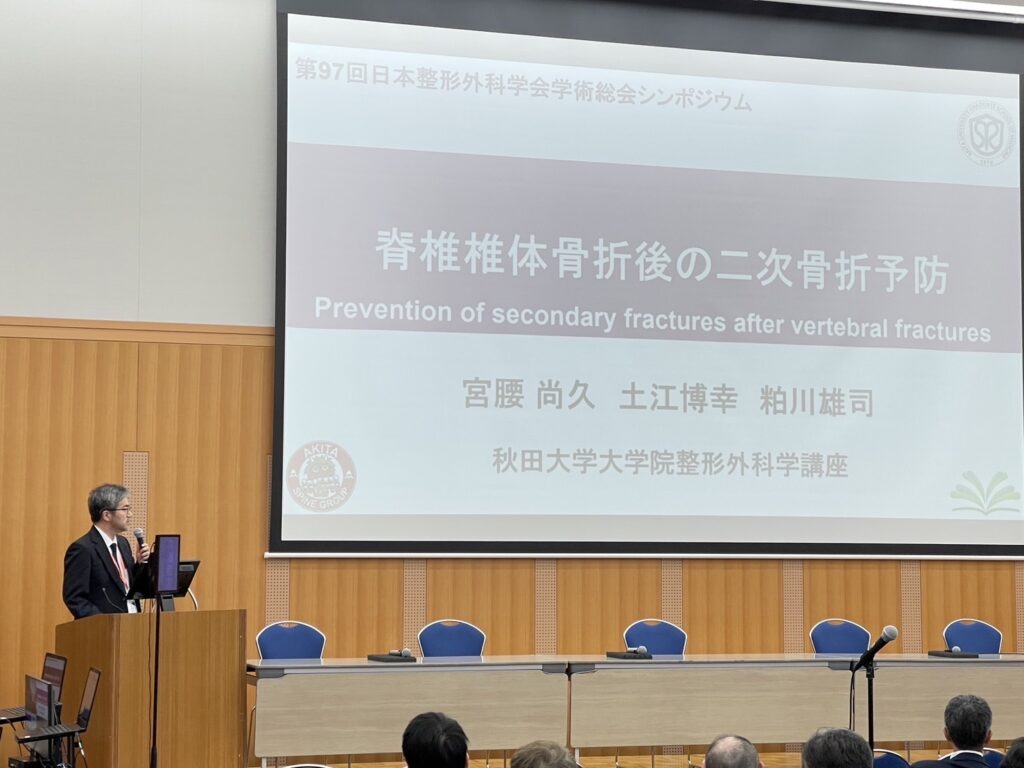
宮腰教授のシンポジウムでのご講演


緊張しまくりの筆者

女子らしくアフタヌーンティーを楽しみました

練習後のバイソンズ