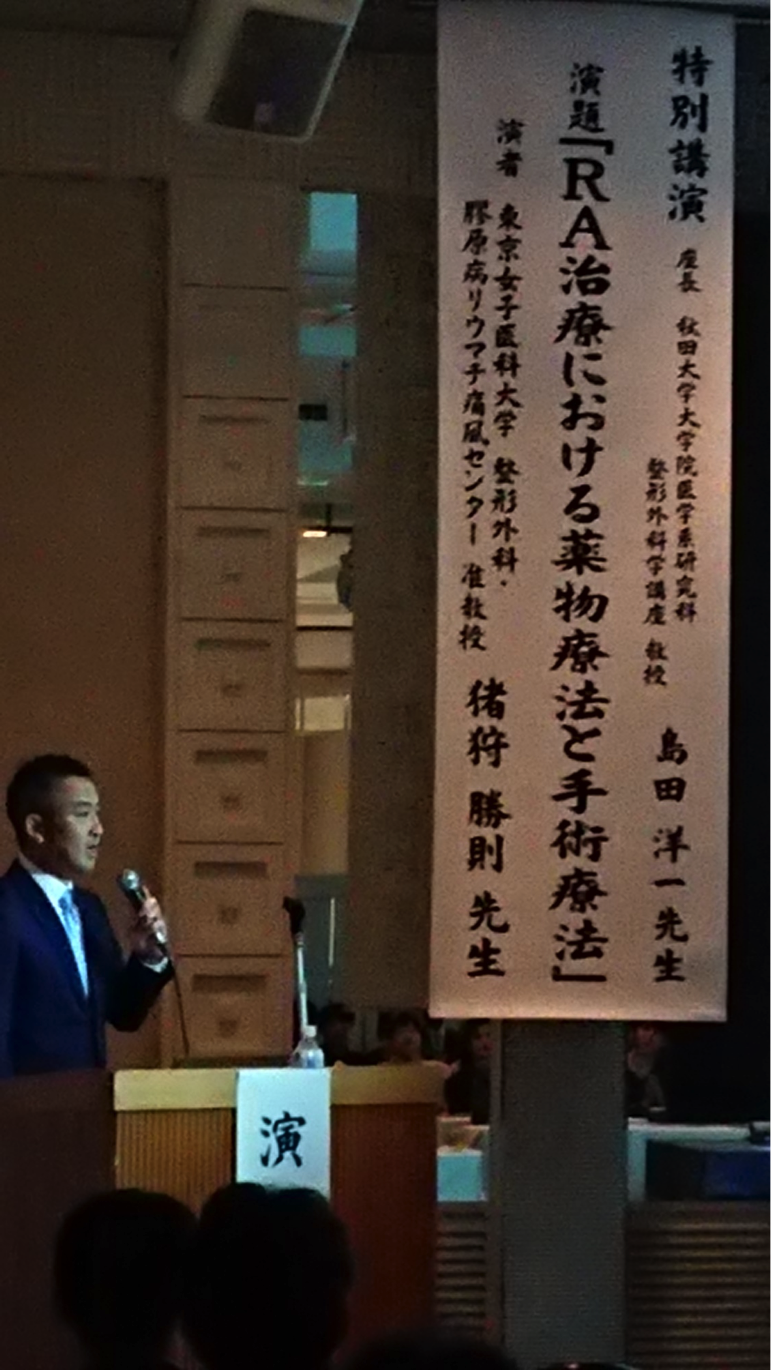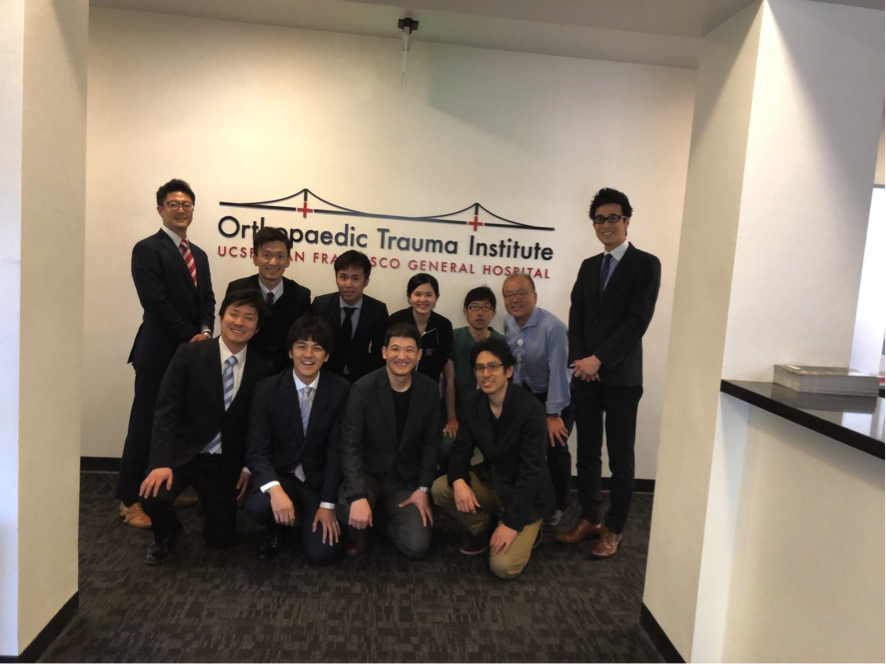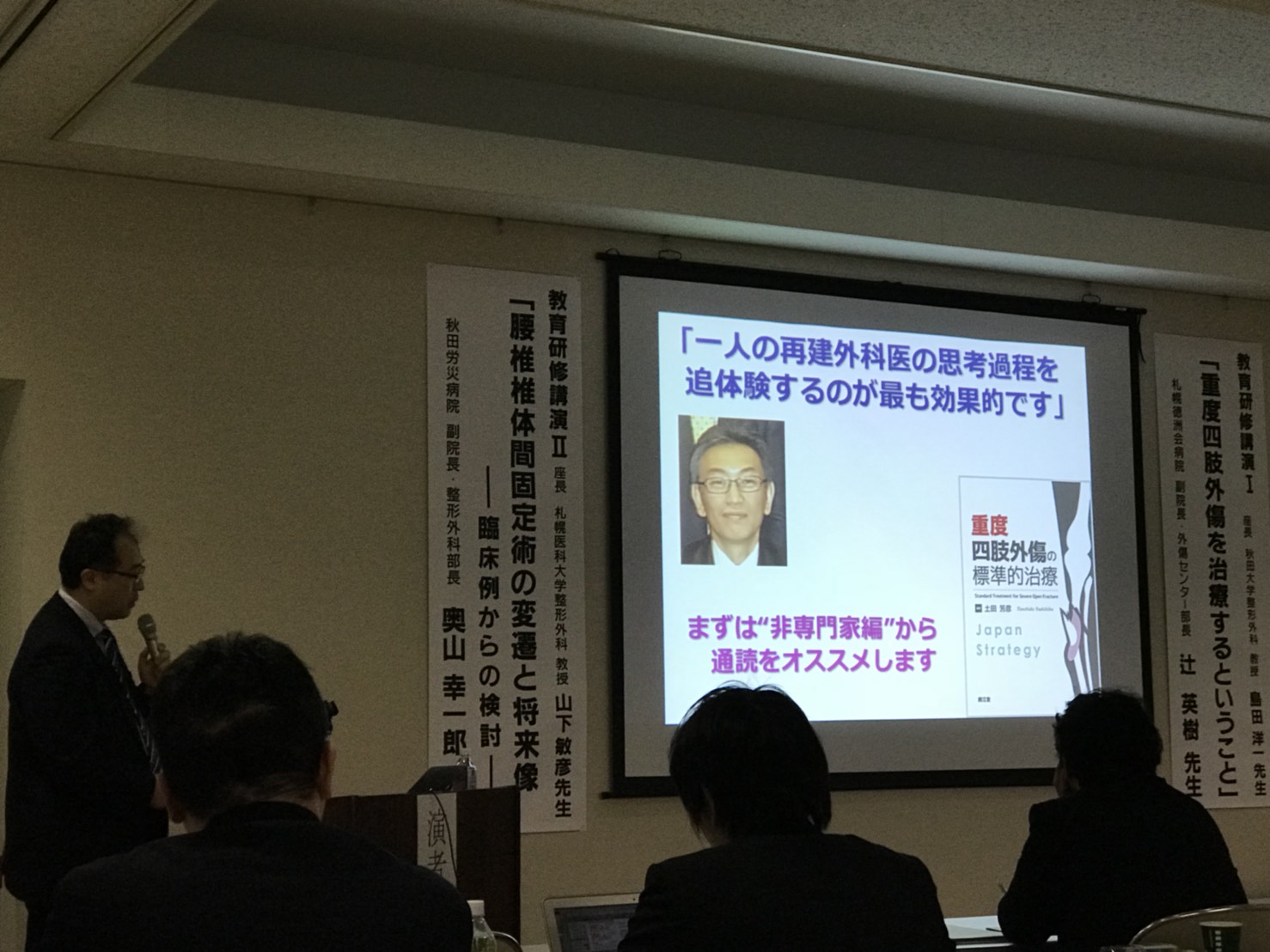令和1年12月12日、第9回こまちリウマチセミナーが開催されました。
一般演題1は、北秋田市民病院の岩本陽輔先生から「RA治療におけるアバタセプトの有効性〜AORA registryから読み解く〜」の題で発表いただきました。秋田県内でのリウマチ患者さんを登録した“AORAレジストリー”の特徴は高齢者が多いことであり、その中でのアバタセプトの使用状況についてわかりやすく報告いただきました。
一般演題2は能代厚生医療センターの伊藤博紀先生から「リウマチ上肢手術の適応とタイミング」の題で発表いただきました。リウマチ患者さんの生活に大きな影響をあたえる“手関節”の手術治療について、手術のタイミングやその実際について解説いただきました。
特別講演は、山形大学医学部附属病院 リハビリテーション部 准教授の高窪祐弥先生から「北欧フィンランドリウマチ診療を目指して−山形循環型病診連携“やらんなネット”5年間の軌跡−」という演題名でご講演いただきました。まずリウマチ治療の基礎について最新の知見を交えながら解説いただき、フィンランド留学中のご経験を多数の写真を交えながら臨場感たっぷりにご紹介いただきました。フィンランドの医療状況、食文化や生活は非常に興味深く、楽しく拝聴させていただきました。日本との相違点として、フィンランドでは一人の患者さんにじっくりと時間をかけて診療することが可能で患者満足度も高く、医師患者間の信頼関係構築もしやすいのかなと思いました。ご留学から帰国後に、高窪先生が山形県で取り組まれたリウマチ診療病診連携システムの構築については、立ち上げから現在にいたるまでの紆余曲折を教えて頂きました。地域連携ネットワークを構築する際のノウハウは私達にとっても大変役立つものであり、貴重なお話を聞くことができました。高窪先生、大変ありがとうございました。
本セミナーで学んだことを、明日からの臨床に役立てて、さらに研鑽を積んでいきたいと思います。