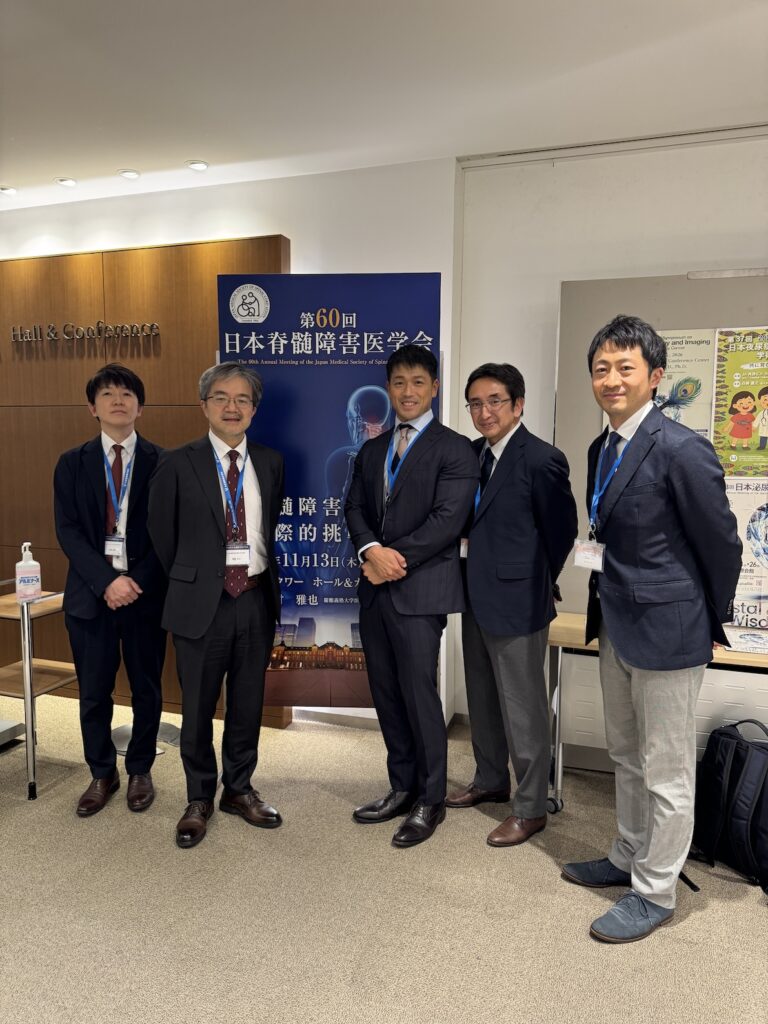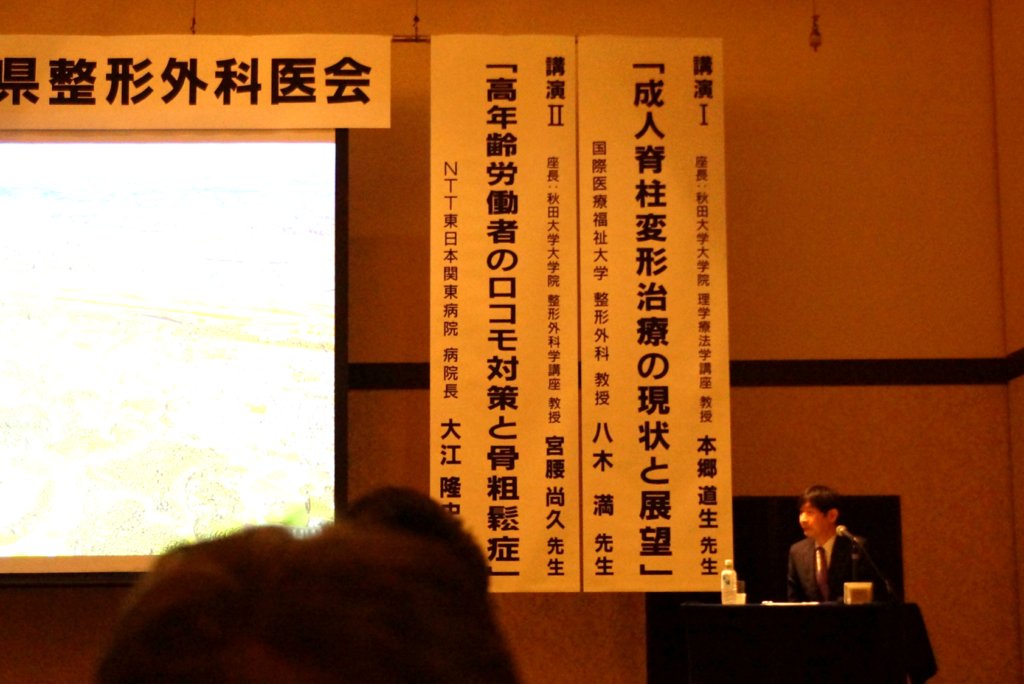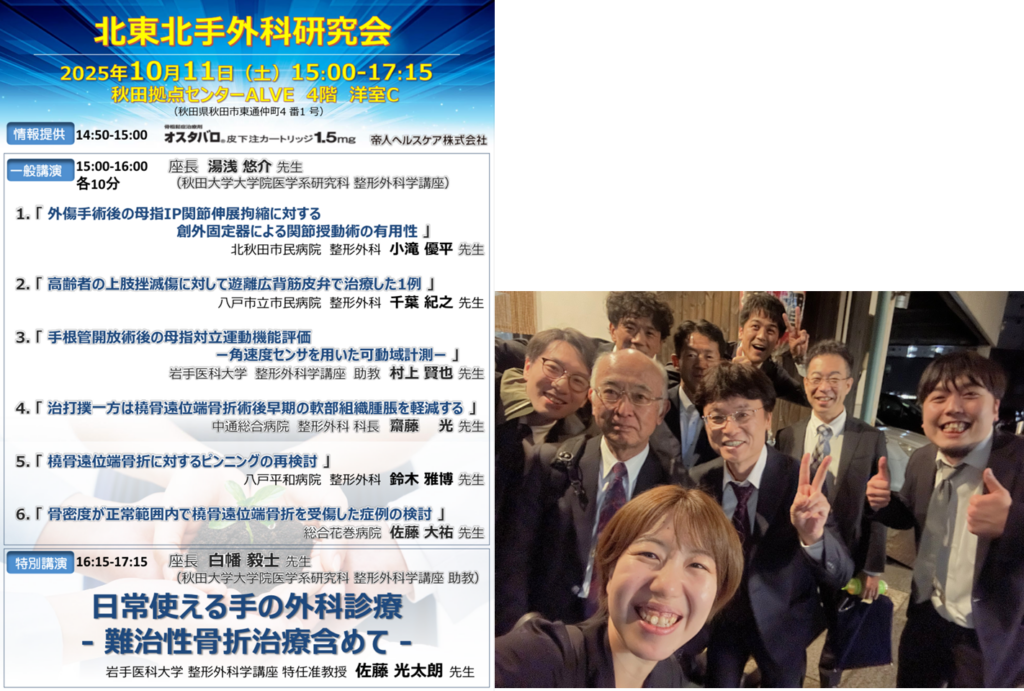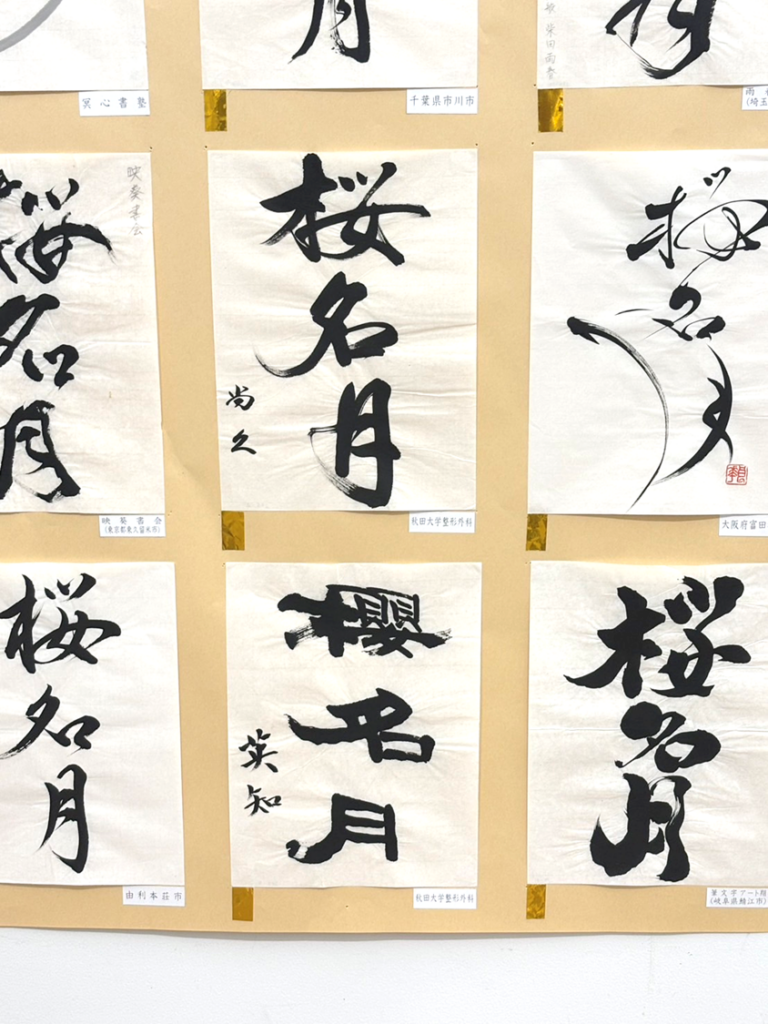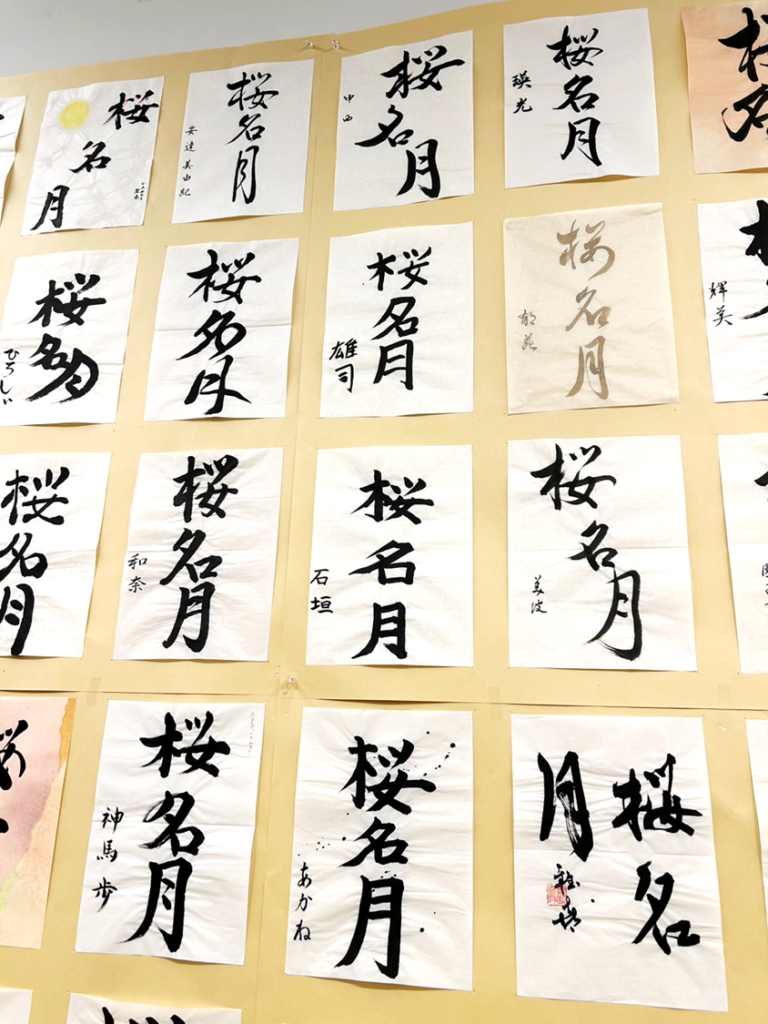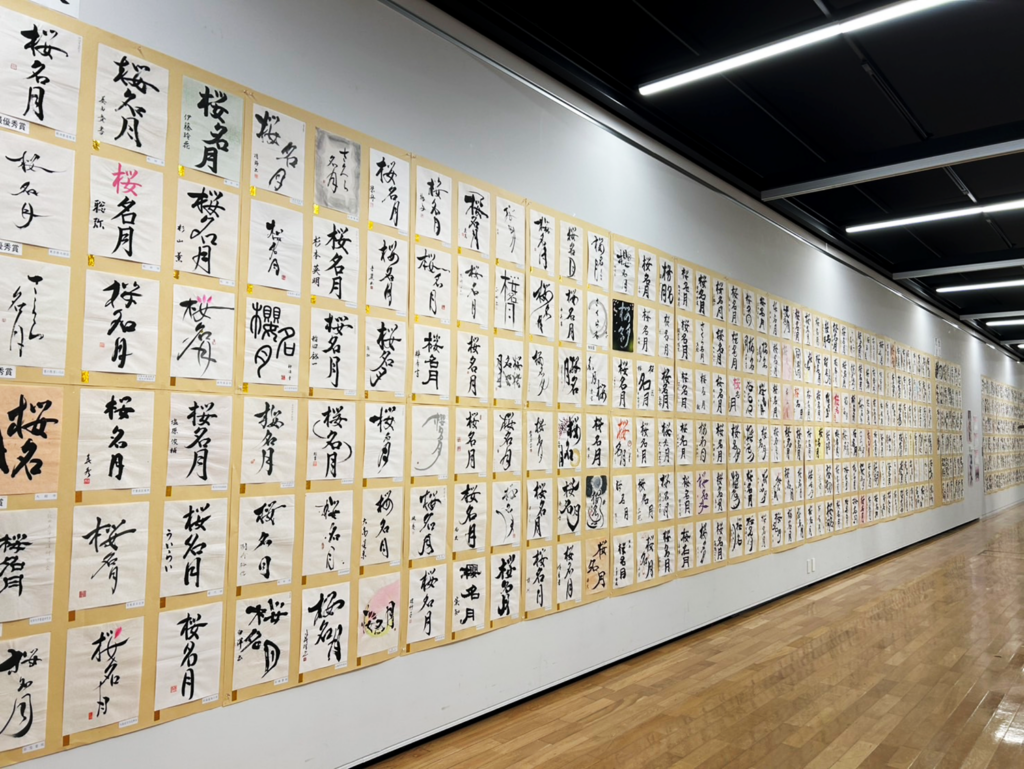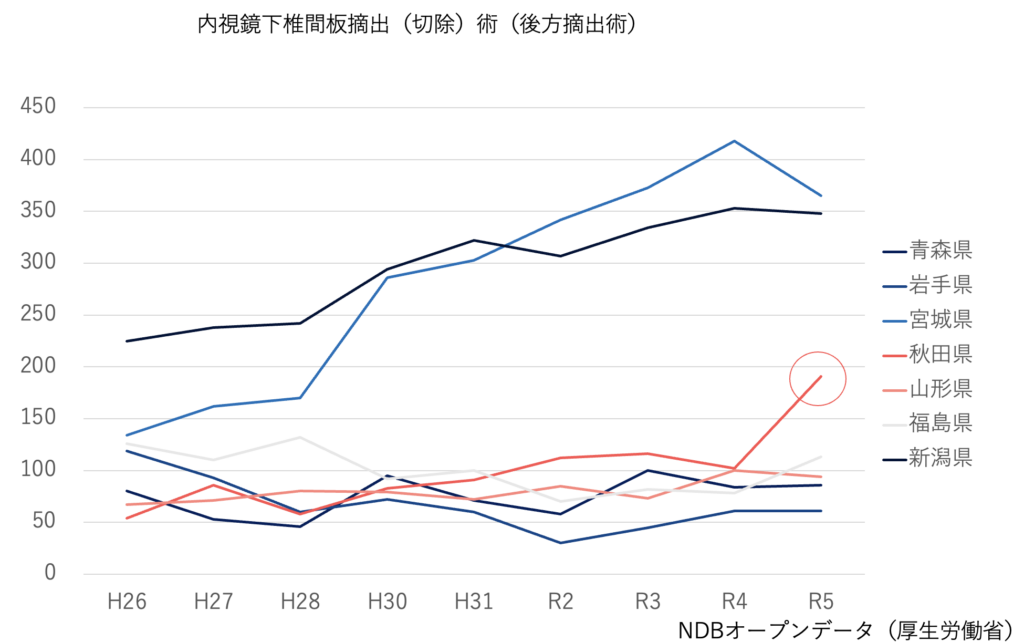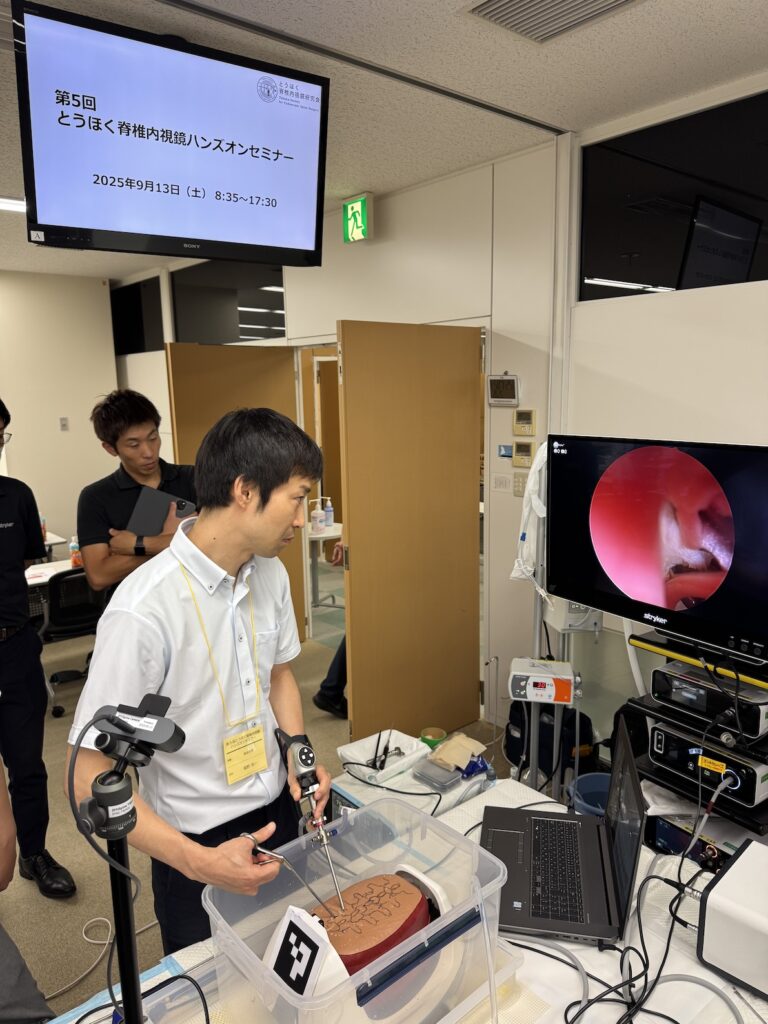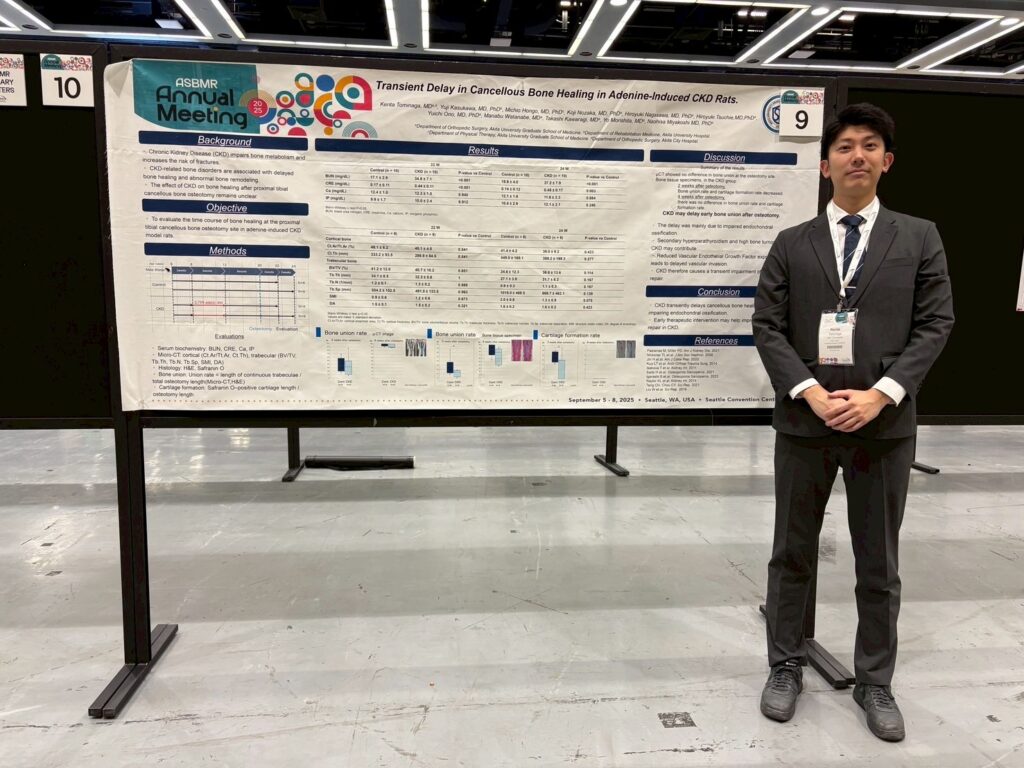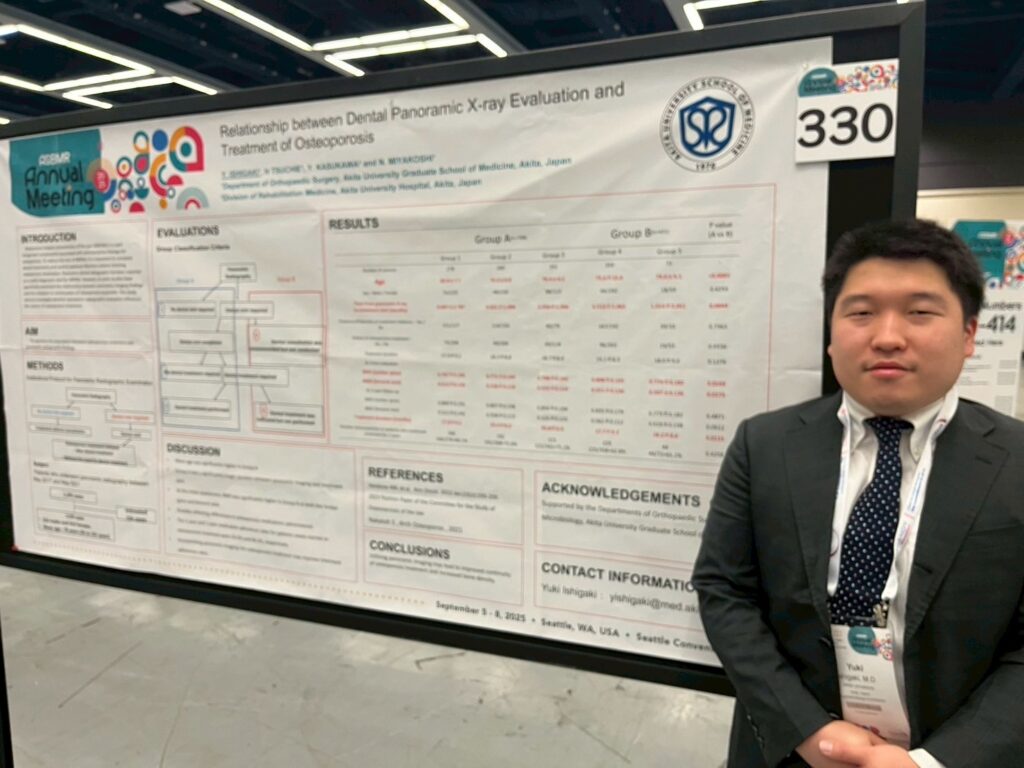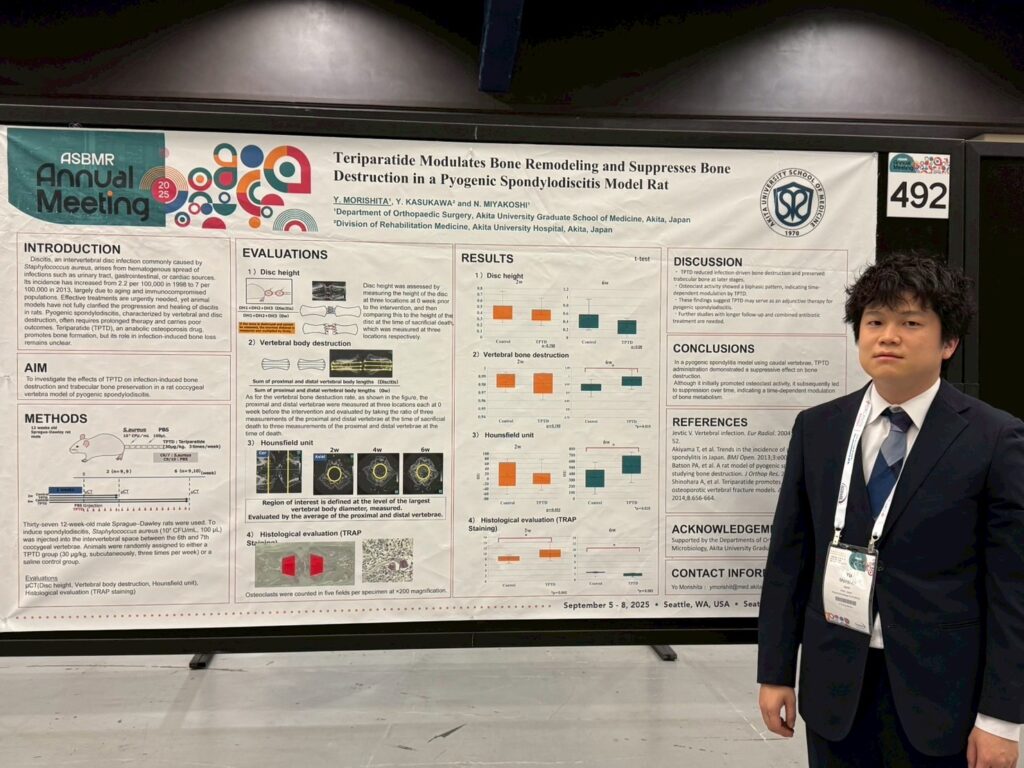2025年9月、米国骨代謝学会(ASBMR)がワシントン州シアトルで開催されました。ダウンタウンのシアトル・コンベンション・センター周辺には世界各国から骨研究に携わる研究者が集い、活気に満ちた4日間となりました。秋田大学整形外科からは富永先生、石垣先生、久田先生、そして私が参加しました。
学会では、基礎から臨床まで骨代謝研究の最前線がオーラルおよびポスターで連日発表されました。当教室からは3演題が採択され、石垣先生、富永先生、私がポスター発表を行いました。
•富永先生:Transient Delay in Cancellous Bone Healing in Adenine-induced CKD Model Rats(CKDモデルラットにおける骨癒合遅延の研究)
•石垣先生:Relationship between Dental Panoramic X-ray Evaluation and Treatment of Osteoporosis(歯科パノラマX線所見と骨粗鬆症治療の関連)
•森下:Teriparatide Modulates Bone Remodeling and Suppresses Bone Destruction in a Pyogenic Spondylodiscitis Model Rat(化膿性脊椎炎モデルにおけるテリパラチドの骨破壊抑制効果)
という演題で発表してきました。
海外研究者の発表を通じて、臨床的知見、研究の設計、評価指標の選択など多くの新しい視点を得ることができ、自身の研究計画に直結するヒントを多数得られました。
学会の合間には、早朝のウォーターフロント・ランで海風を感じ、パイクプレイス・マーケットやスペースニードル周辺を散策。都市のスケール感と豊かな自然が共存するシアトルは、学びと交流の舞台としても非常に魅力的でした。
また夕食では、アメリカらしい大きなステーキやシアトルで有名なシーフードを堪能しました。どちらもアメリカサイズの大量の料理でフードファイトの様相を呈しました。特にシーフードレストランでは机いっぱいに料理が並び、石垣先生が店員さんに集合写真を頼もうと、「Can I take a picture?」と声をかけた際には、レストラン内が和やかな笑いに包まれ、楽しいひとときとなりました。
帰りは、私が宿にリュックを忘れて、シアトルの街でみなさんをお待たせするという珍プレーをかましましたが、総じて素晴らしい学会参加だったと思います。
今回のASBMR参加を通じ、自分に不足している点と次に進むべき方向を改めて確認できました。貴重な機会を与えてくださった宮腰教授、粕川准教授をはじめとする医局の先生方に深く御礼申し上げます。今後は学会で得た知見を研究・診療に還元し、成果として形にしていきたいと思います。