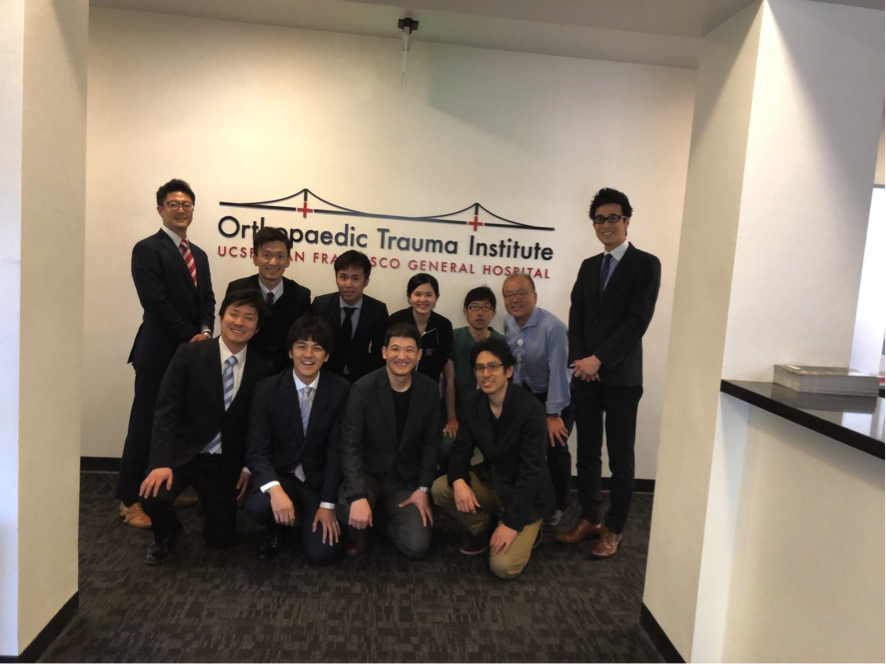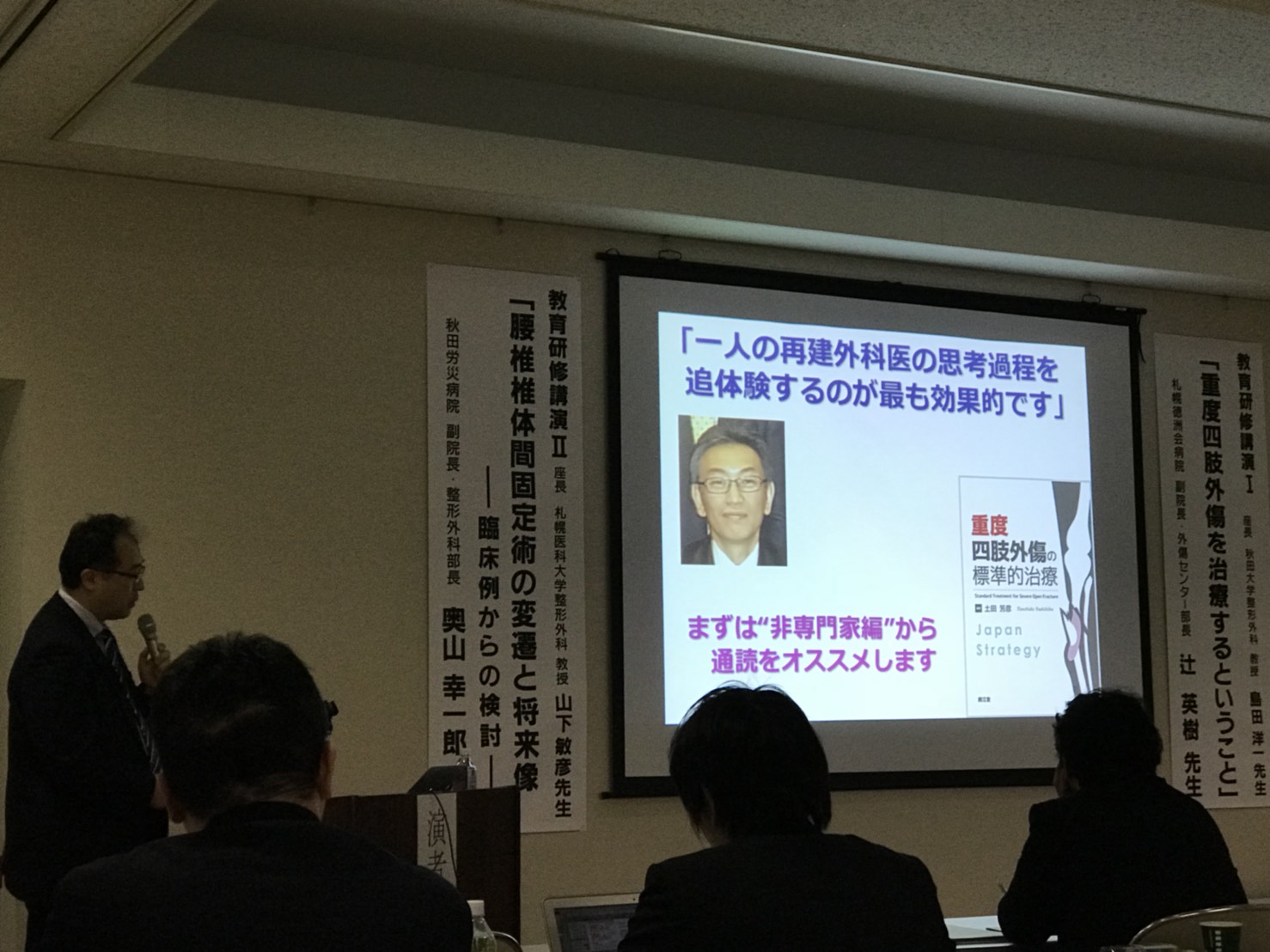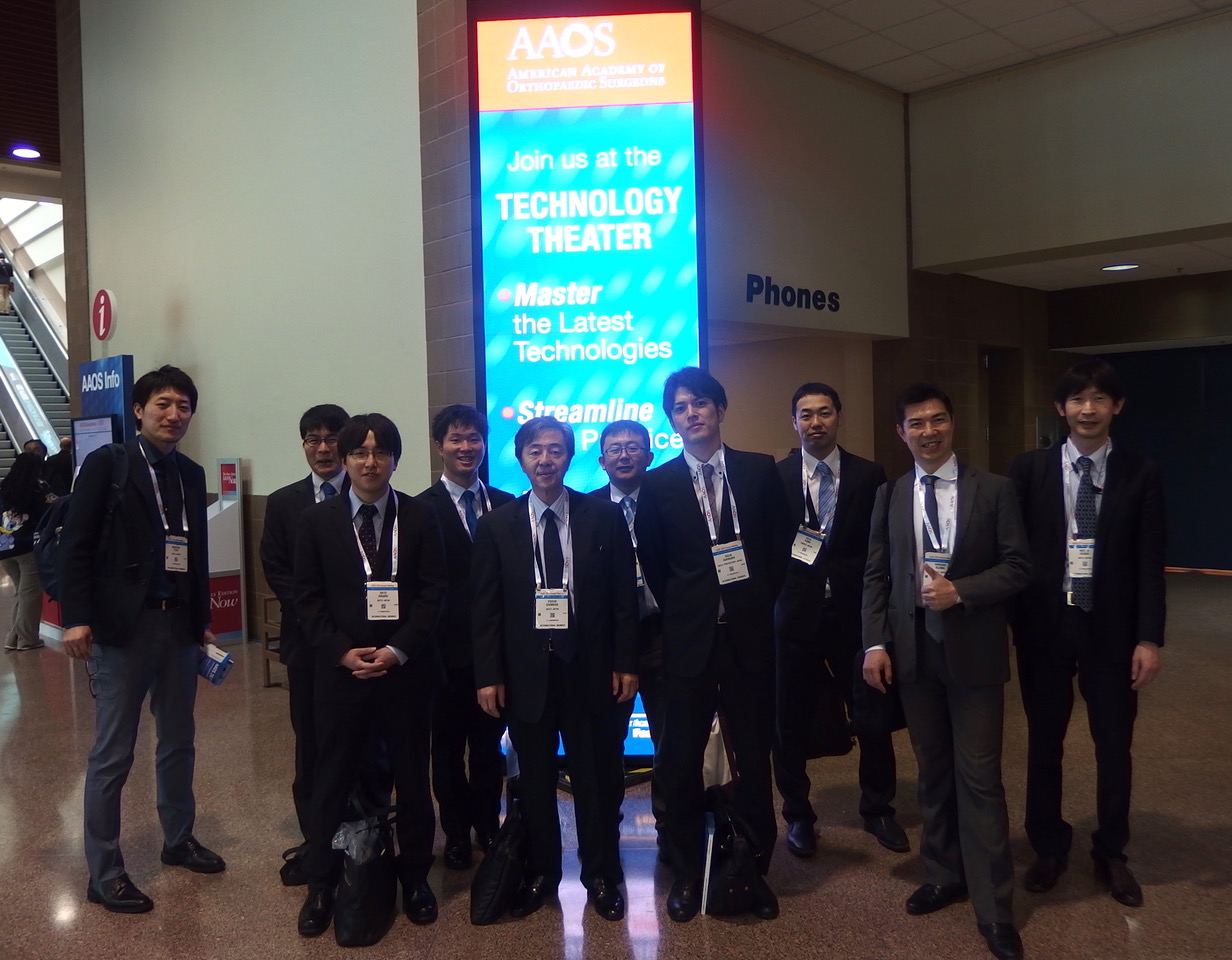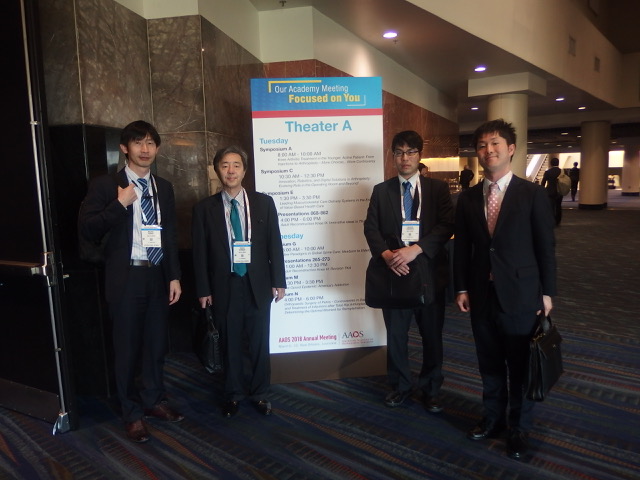4月22日〜30日と長期の時間をいただいて、サンフランシスコ外傷セミナー・OTIコース・キャダバーに参加させてもらいました。
サンフランシスコはほぼ毎日が快晴で驚くほど天気がよく過ごしやすい気候でした。風がつよく時々肌寒く感じることもありましたが、皆半袖で過ごすくらい暖かく良い気候でした。
まず最初は岡山大学の野田先生・福岡整形外科病院の徳永先生・秋田大学の野坂先生が講師のキャダバーコースに参加しました。足部・膝・股関節・さらには骨盤と下肢をほぼすべて網羅するような内容になっており、手術の皮膚切開や解剖上のピットフォールなどをとても丁寧に教えていただきました。コース外のことも自分の興味が部分をさらに掘り下げて学ぶことができました。また同世代・もしくは自分たちよりも若手の先生と一緒になって行うことで、自分たちに足りていない点や他の大学の話も聞けてとても刺激になりました。時間に余裕ができると本来のキャダバーコースに含まれていなかった骨盤の解剖などもご指導いただき最初から最後までとても充実したキャダバーコースでした。
翌日からは島田洋一教授と大学時代の同期に当たり、現在Zuckerberg San Francisco General Hospitalで勤務している長尾先生の元に施設見学と症例検討をさせていただきました。日本の病院とはだいぶ勝手が違うことはなんとなくは理解していましたが、改めて説明を受けると驚きの連続でした。入院期間の短さや、手術室・術後の麻酔管理のための場所の確保などとても興味深く見学をさせてもらいました。また日本よりも各職種の仕事が明確に細分化されており、また違った世界なんだと改めて実感をさせられました。
外傷セミナーでは現在行われている治療の選択方法や、体の各部位ごとのピットフォール、トラブルの対処方法などを10分単位という短い講義で聞いてきました。英語がなかなか不得意な自分でも頑張ればかろうじて聞き取れるような内容であり、少し、本当に少しは英語力も身についたのではないかと思っています(なんとなく聴き慣れただけかもしれません)。さらには肘や手関節などで模擬骨を使った手術手技のハンズオンなども受け、盛りだくさんのセミナーでした。
ゴールデンゲートブリッジや、フィッシャーマンズワーフ、ユニオンスクエアなど有名どころへいき普段触れることのないアメリカの文化に触れてきました。日本では見ることがないくらい広大な自然に触れることができとても楽しい時間を過ごしました。
最後になりますが、今回OTIの長尾先生をはじめ、たくさんの先生方にアメリカの地でお世話になりました。ありがとうございます。また今回の機会をくださった島田洋一教授、宮腰尚久准教授をはじめ、通常業務や当番を担当してくださった各グループの先生、大学院の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。