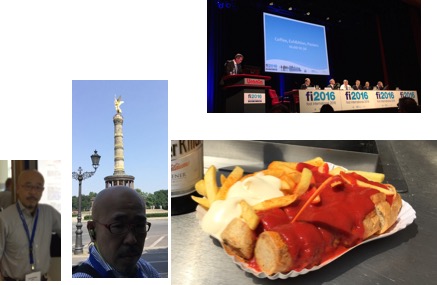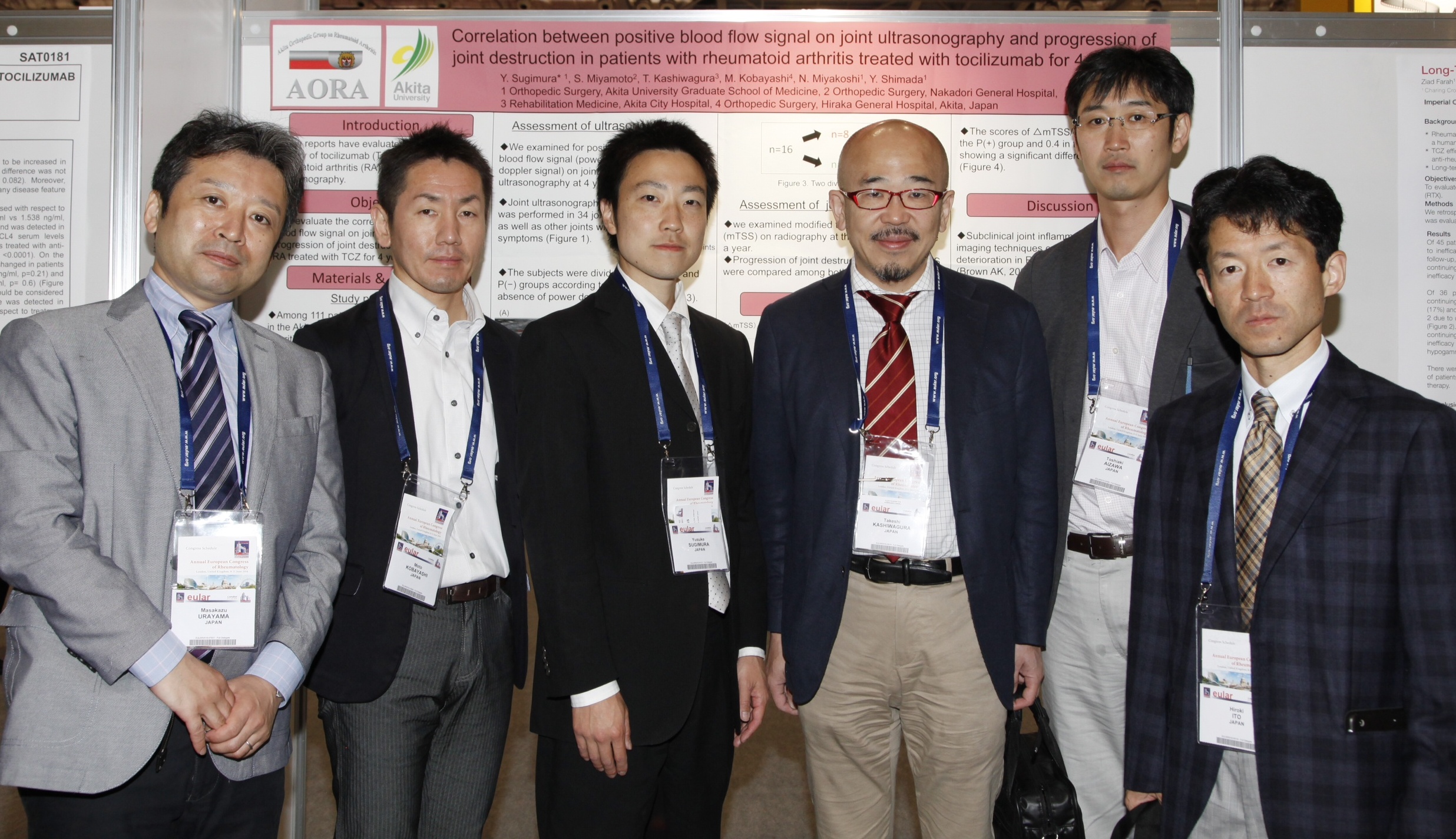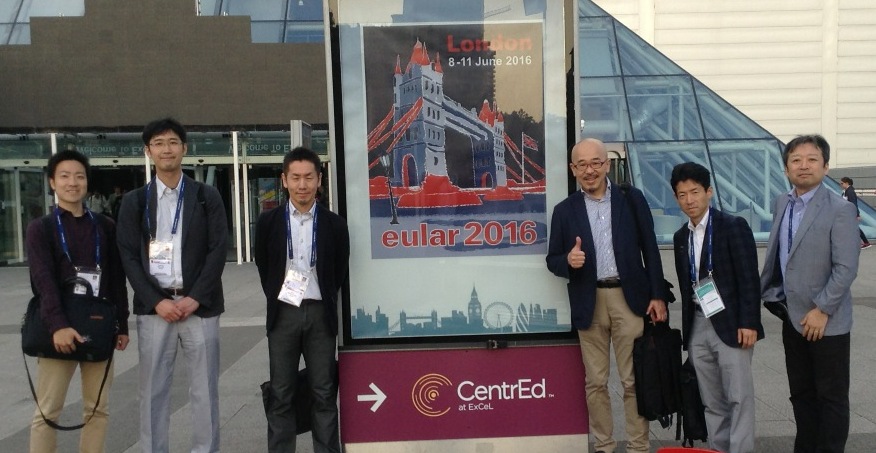去る7月21日,「第4回こまち疼痛を考える会」がビューホテルで行われました.
一般演題では,斉藤公男先生が秋田・弘前の若年者の体幹バランスの比較や、スポーツ強化指定中学生のメディカルチェックについて興味深い研究結果をお話しいただきました.
また,齋藤英知先生からはTKAや様々な骨切り,靭帯再建術における疼痛管理の工夫や,その最新の知見についてお話しいただきました.
さて,特別講演では 弘前大学大学院医学研究科リハビリテーション医学講座 教授 津田英一先生にご講演をいただきました.弘前大学の各診療科が参加し,青森県の平均寿命・健康寿命の延伸を目的に行っている岩木健康プロジェクトや,住民健診におけるロコモの有無や,全身の筋力・柔軟性・動的/静的バランスの関係性などについて,またそれらと膝痛との強い関連性をわかりやすくお話しいただきました.地域の住民に根差したお話であり,少子高齢化では負けず劣らずの秋田県整形外科医として,非常に興味深い内容でありました.
また,疼痛管理に関しても詳しく教えていただきました.特に心に残ったのが「人工膝関節術後の医師満足度と,患者満足度の相関が低い」ということでした.衝撃的なことでもあり,よくよく考えれば当然のことでもあり・・・これは人工膝関節だけでなく,その他すべての手術・日常診療にかかわることであり, 自分を律するために心に焼き付けておきたいと思います.
また,津田先生は青森ワッツのチームドクターもされており,ノーザンハピネッツのチームドクターをしている当科医局員として,バスケも、陸上も、野球も、臨床も(当然剣道も.)負けてはいられないと心が奮い立ちました.
津田先生,今後とも御指導のほどよろしくお願い申し上げます.