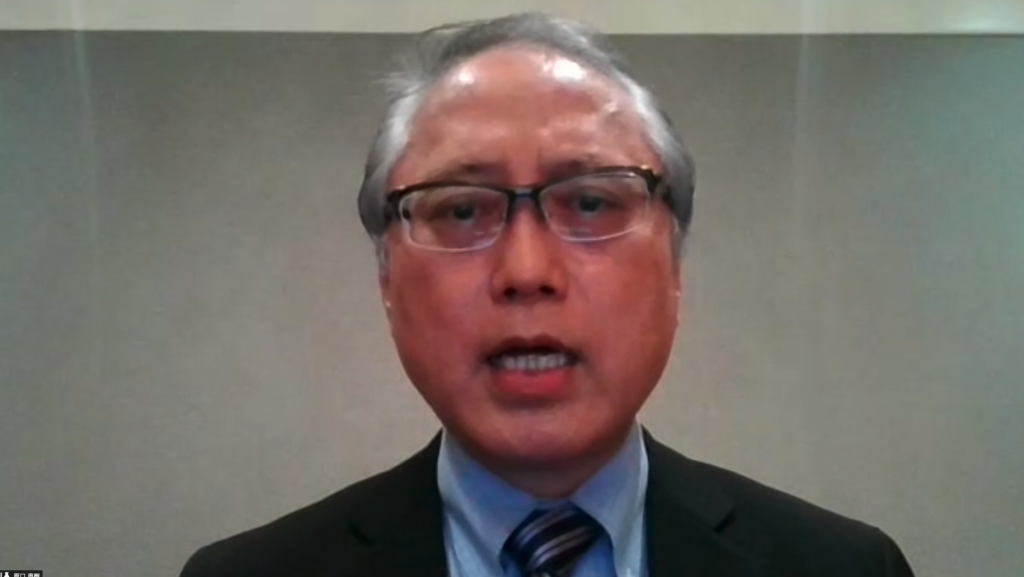2022年2月19日、第29回秋田県スポーツ医学研究会がオンライン開催されました。
下記、プログラムからの転載になりますが、それぞれがとても興味深い内容ばかりで、スポーツの幅広さを実感いたしました。ご講演いただきましたシンポジストの先生方、誠にありがとうございました。
【シンポジウム1】スペシャリストからの提言
1)「SARS-CoV-2 mRNAワクチン接種後の抗体価」
富樫 賢 先生 (あきた 腎・膠原病・リウマチクリニック)
2)「アスリートと生活習慣病」
森井 宰 先生 (秋田大学 糖尿病・内分泌内科)
3)「秋田県医師会「明日はきっといい日になる」ロコモダンスプロジェクト」
高橋 郁子 先生 (秋田大学 小児科)
4)「秋田県女性ジュニアアスリートと女性医学指導の実態」
小野寺 洋平 先生 (秋田大学 産婦科)
【シンポジウム2】障がいを超えた地域スポーツの取り組み
- 「スポーツを通した子どもたちとの関わり」
佐藤 理枝子 先生 (秋田県立医療療育センター リハリハビリテーション部門)
2)「eスポーツでつくる新たな参加の形」
若狭 利伸 先生 (社会福祉法人北杜 障がい者支援施設ほくと)
3)「義足スポーツサークルAmbeinsについて-スポーツ活動からみる義足の可能性-」
佐藤 陽介 先生 (秋田厚生医療センター リハビリテーション科)
4) 「パラアスリートサポートの最前線 〜 Tokyo 2020 Paralympic Games 活動報告 〜」
藤井 昌 先生 (市立秋田総合病院 整形外科)
特別講演1は、「最期まで自分の脚で歩くためのスポーツ疫学研究~こどもからトップアスリートまで~」と題して、千葉大学大学院国際学術研究院准教授(千葉大学大学院 医学研究院 整形外科学)山口智志先生にご講演いただきました。
山口先生は整形外科医でありながら、教育学部関連のご所属ということで、疫学をもとにしたアプローチを主体にご講演いただきました。ロコモーティブシンドロームへの介入の重要性についてデータを元にご説明いただき、改めて積極的な介入の必要を実感させていただきました。また、ヘルスリテラシーを高めるという点について、インターネット上に誤情報が多くあるからこそ大切な介入点だと思いました。アキレス腱の治療は日本は手術が増加傾向、子供は身体が硬いのが普通、扁平足は痛みの原因でない、アスリートのトランスジェンダーなど多くの話題で、疫学調査から得られる学びをご教授いただきました。
また、東京オリンピック2020で金メダル獲得のスケートボード種目の、裏側のお話も興味深く、テレビ中継の裏ではかなりのご苦労があったことを知ることができました。
スポーツ障害について、疫学調査から介入を始めるというお考え、とても素晴らしくぜひ秋田でも取り組みたいと思います。
特別講演2は、「総合診療と喘息・スポーツ」と題して、秋田大学大学院医学系研究科 総合診療・検査診断学講座 教授 植木 重治先生にご講演いただきました。
喘息の基本的な知識から、IgEが日本で発見された(石坂公成先生)こと、IgEが関係しない喘息(非アトピー型喘息、成人発症)があり、気道の上皮障害などが原因で生じること、整形外科で多用するNSAIDsに関連するアスピリン喘息(N―ERD)について、アスピリンに対するアレルギーではない=アレルギー学的検査では診断不能、問診が重要など、なかなかブラッシュアップできずにいた知識について、とてもわかりやすくご教授いただきました。
アスリートの喘息有症頻度が一般より高いこともあり、プレーへの影響がどうなのか気になっていたのですが、オリンピックのメダリストは参加者の中でも喘息有症率が高いということで、コントロールできているとプレーに影響しないということで、アスリートの支えになる内容でした。
また、総合診療部で行われている渡航外来では、英文診断書・証明書の作成や、ワクチン接種、マラリアや高山病予防薬などに取り組まれていらっしゃり、スポーツ選手にも大切な存在が身近にあることを知りました。
講演中、植木先生が不意に発せられた、「スポーツを通して全人的にみる」という表現が素敵だなと思いました。スポーツが好きな医療者は、スポーツを通してその人そのものをみたいのかもしれません。
最後に、秋田県スポーツ医学研究会では、パラスポーツ推進ワーキンググループを作り、パラスポーツ(障がい者スポーツ)の普及にも取り組んでまいります。