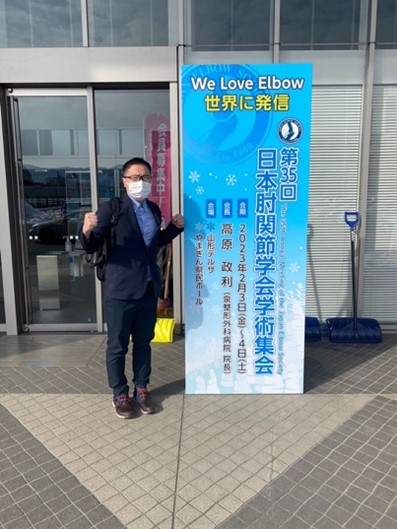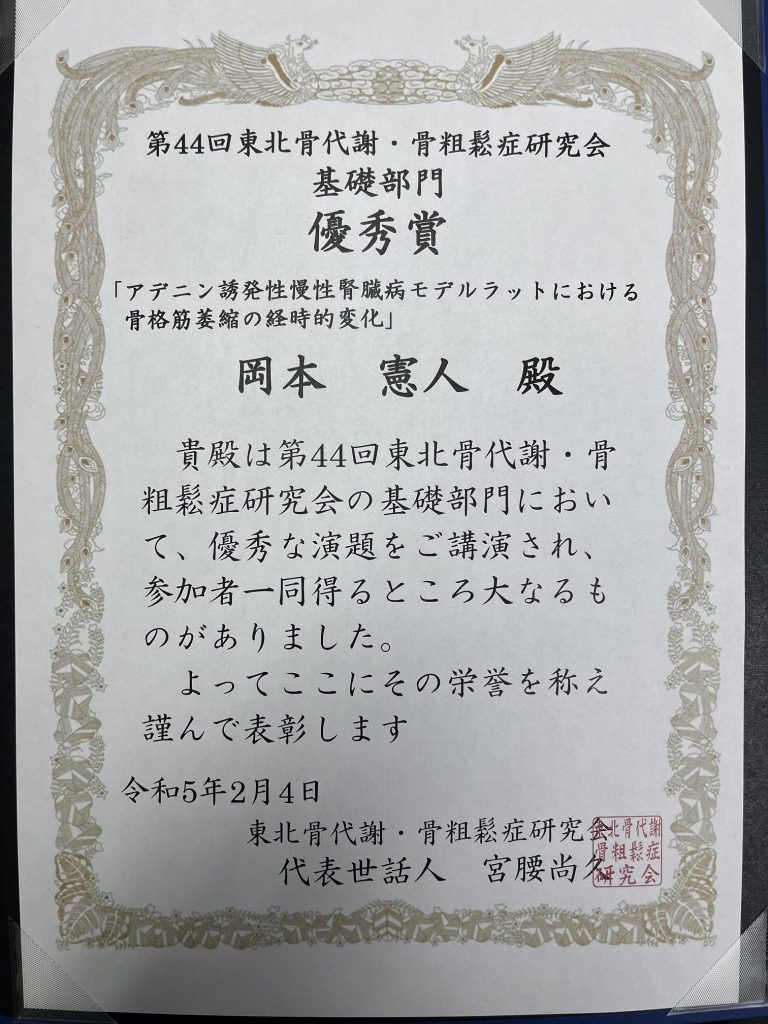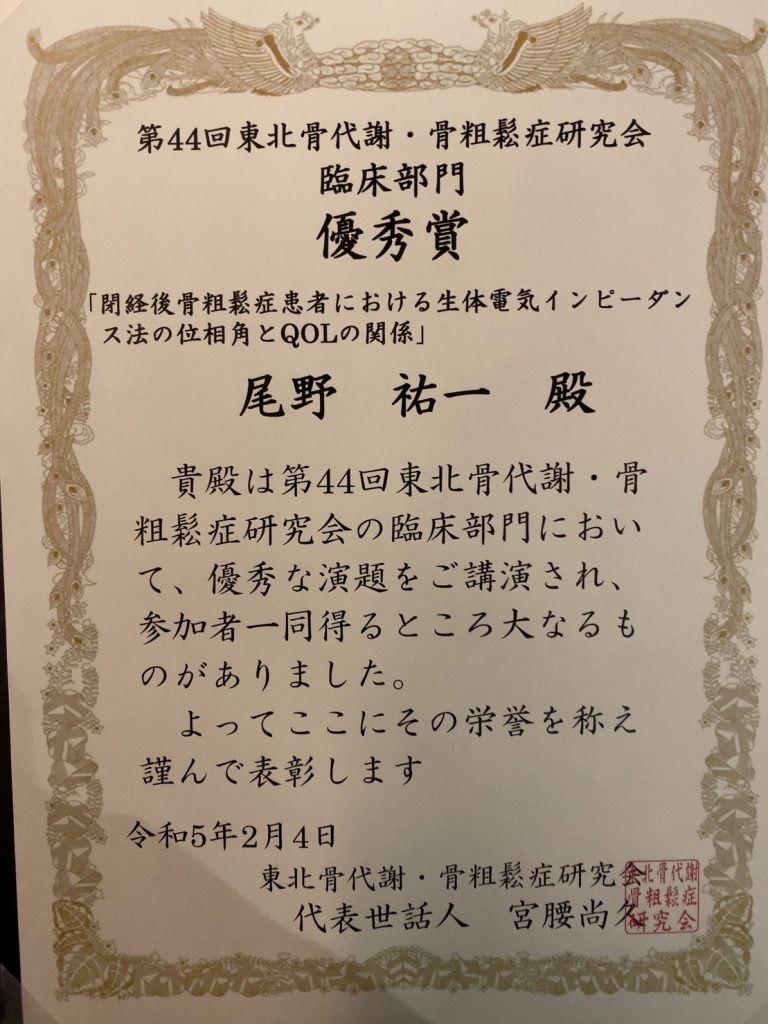2023年3月4日秋田市にぎわい交流館AUで第60回秋田県脊椎脊髄病研究会が開催されました。今回の当番幹事は秋田赤十字病院の尾野祐一先生が務めておりました。Zoomと現地のハイブリッド開催となり少しずつ現地へ足を運べる回数が増えてきたように思われます。最近はコロナ感染も少しずつ落ち着いてきており3月中旬からはノーマスクが可能となり5月には5類となることが決まっております。今後も現地開催が増えることを祈っております。
研修医や若手整形外科への基礎講座として由利組合総合病院の菊池一馬先生、秋田大学医学部付属病院の工藤大輔先生、能代厚生医療センターの佐々木寛先生からそれぞれ出血への対応、硬膜損傷、髄液漏への対応、術後感染への対応をレクチャーしていただきました。脊椎外科を目指す研修医や若手の先生にはとても有意義かつ大事な内容であり、臨床に役立つ内容でした。
また今回は記念すべき第60回であり、記念企画として秋田大学医学部付属病院の本郷道生先生からこれまでの秋田県脊椎脊髄病研究会を振り返ってというお話をいただきました。第1回から現在まで、写真や懐かしいエピソードを交えたお話を聞くことができました。今後の展望も考えられており自分たちもその一員として成長していきたいと思いました。
一般演題は5題あり、珍しい症例や治療に難渋する症例の報告が多く、活発な議論がなされておりました。その中でも記念すべき第60回の最優秀演題賞に選ばれたのは、秋田赤十字病院の浅香康人先生でした「ブラウンセカール型の症状を呈した上位頚椎OPLLを伴う非骨傷性頚髄損傷の一例」についての報告であり、治療に難渋する症例で多くの意見が飛び交っておりました。
特別公演は稲波脊椎・関節病院院長の高野裕一先生より「脊椎脊髄疾患に対する内視鏡アプローチの最新のトピックス」についてご講演いただきました。ご自身の経験から早期離床の必要性を強く確認し内視鏡へ移行した経緯、従来法からMEDやLIFへの移行や注意点のお話、FESS(full-endscopic
spine surgery)やUBE (unilateral biportal endoscopy)などに関する最新のお話などがあり大変興味深く拝聴いたしました。
来年にはさらにコロナ感染が落ち着き、第61回も現地の空気を感じながら開催されることを祈っております。ご講演いただいた先生方、本会開催に当たりご尽力いただきました方々に心より感謝申し上げます。