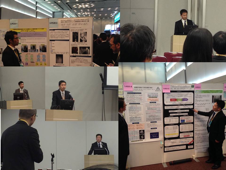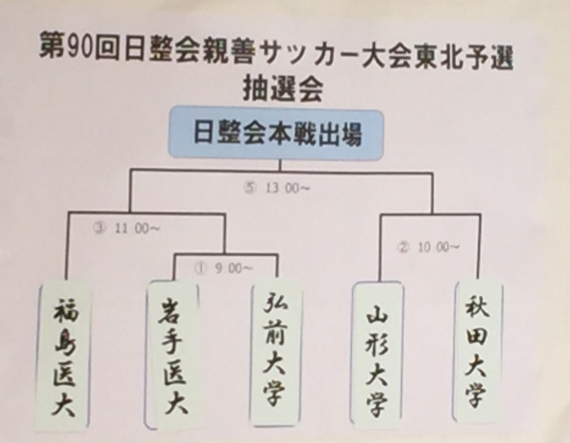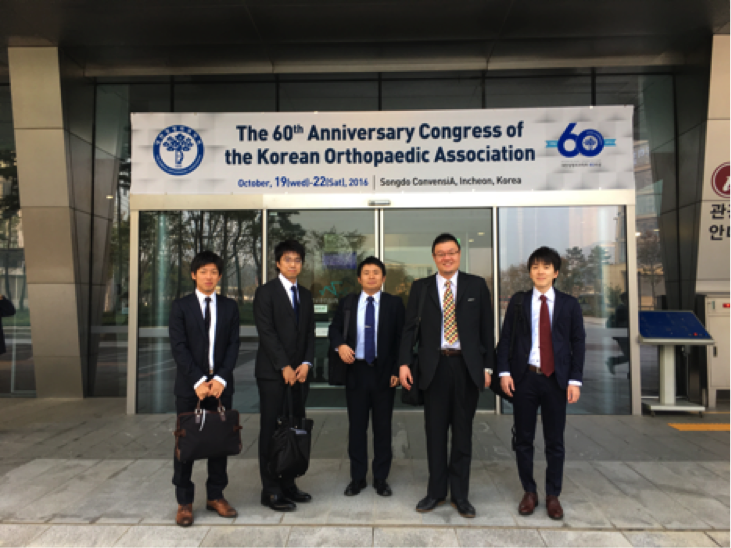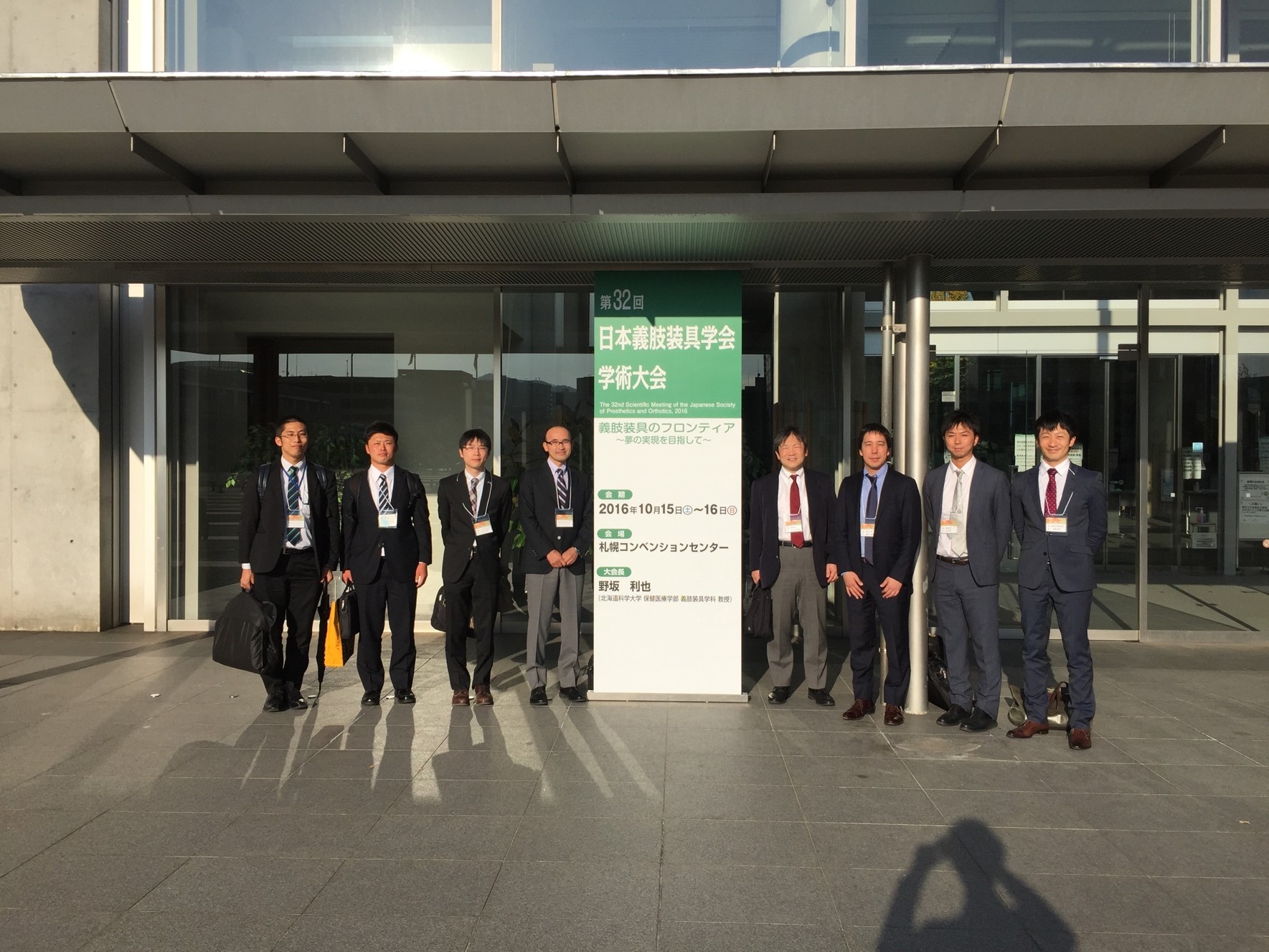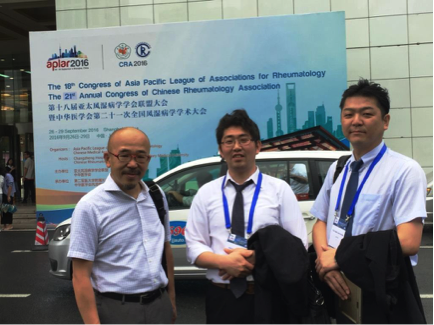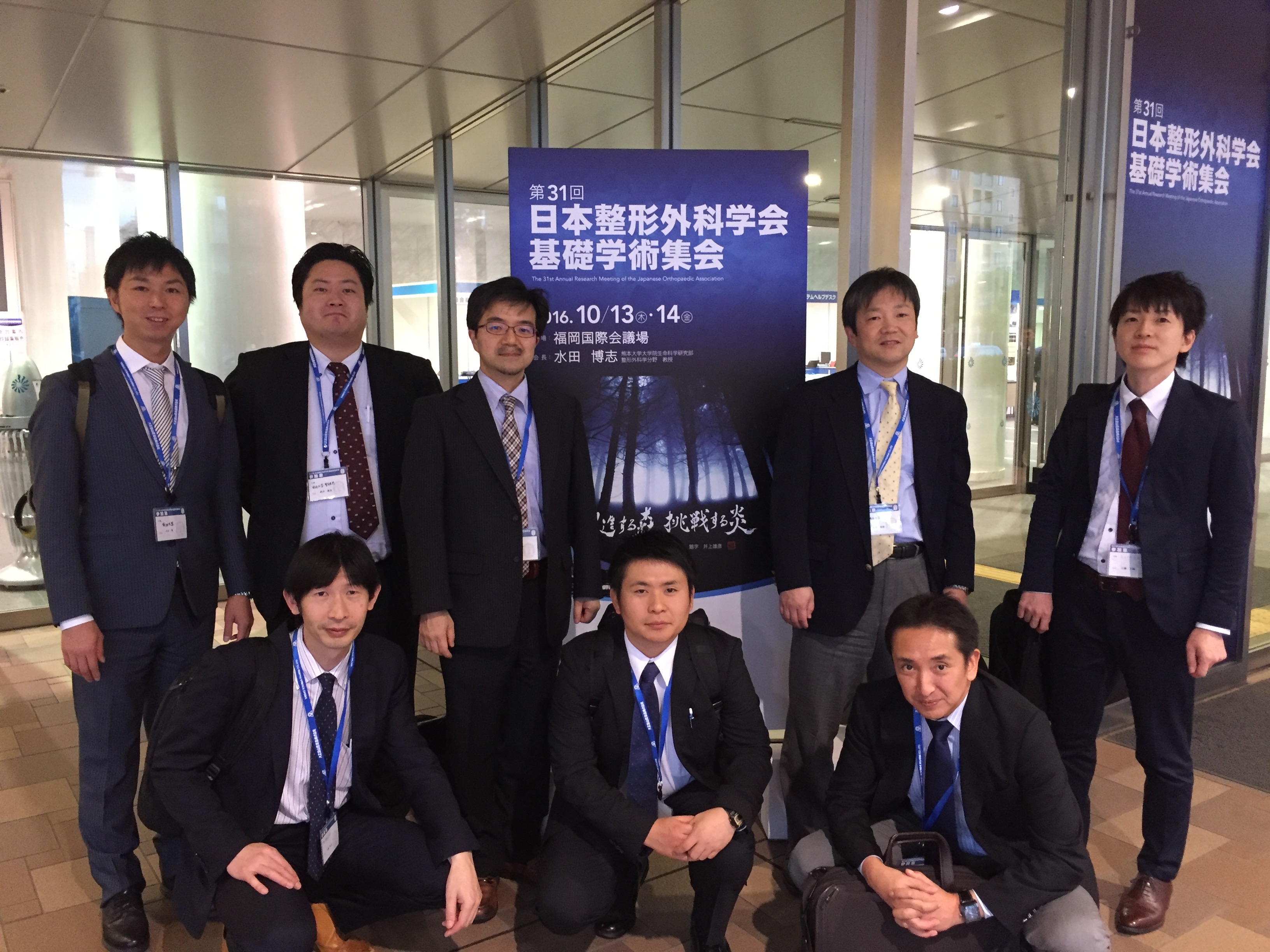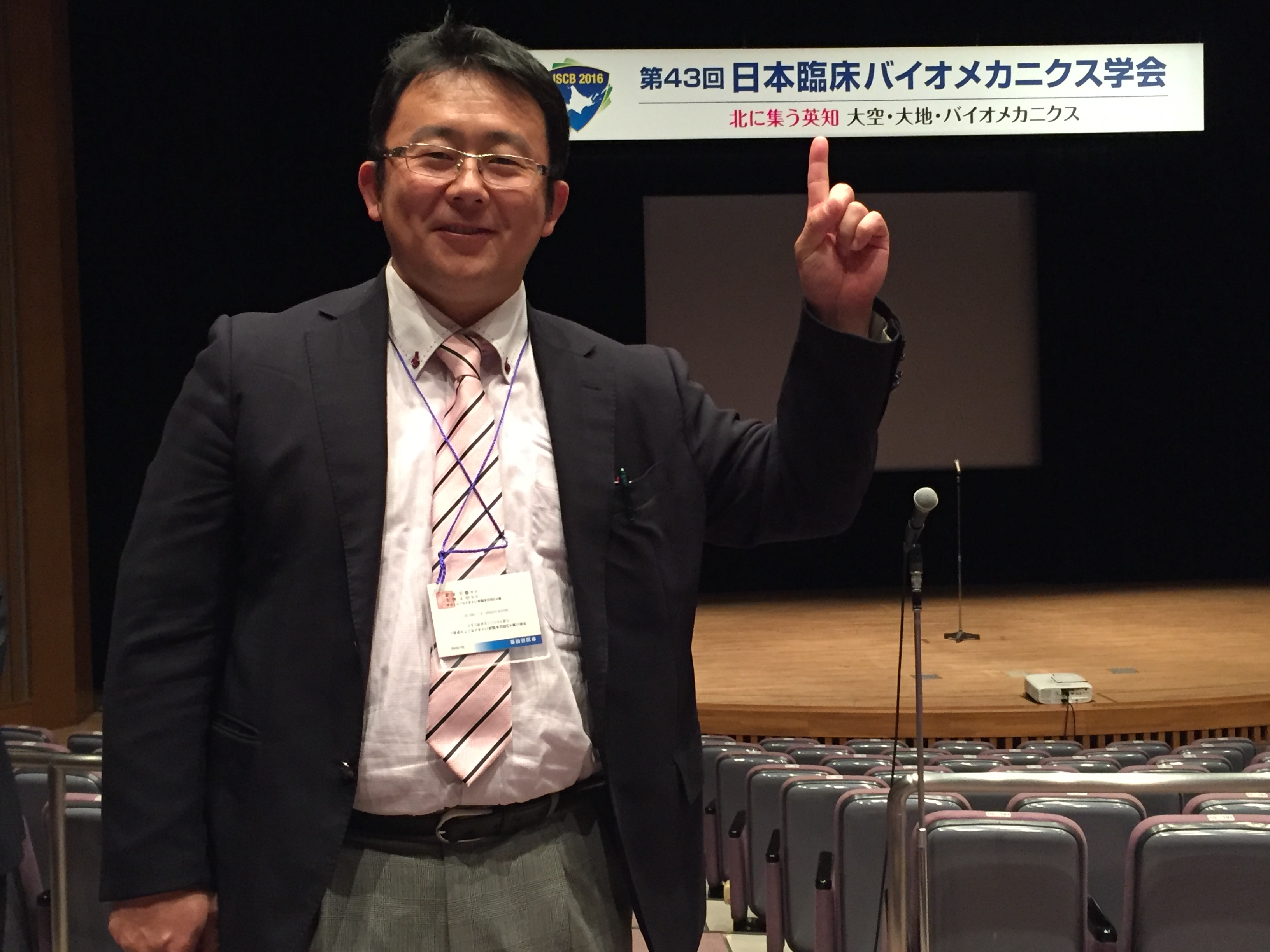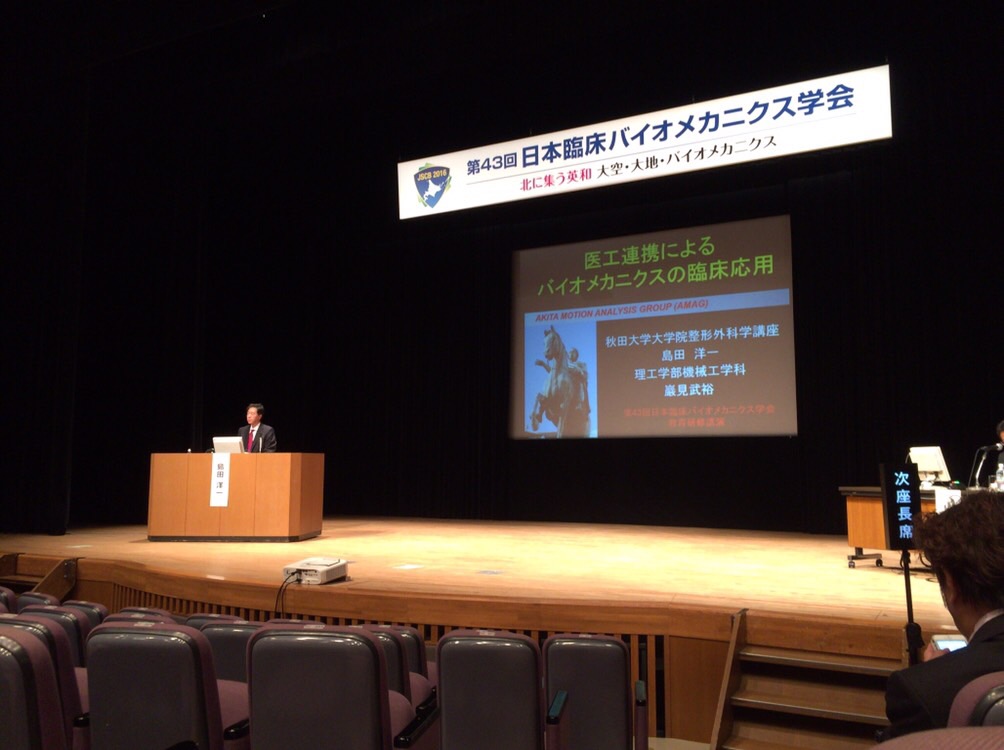2016年11月4-5日の2日間、大阪国際会議場にて、第43回日本股関節学会学術集会が開催されました。秋田からは、Akita Hip Research Groupの山田晋会長、小西奈津雄副会長、久保田均副会長、田澤浩vice director、加茂啓志先生、奥寺良弥先生、河野哲也先生、木島の計8名が参加致しました。
学会長は、関西医科大学整形外科教授の飯田寛和先生です。今回のテーマは「Back to the Future」。この学会は1974年に第1回股関節研究会として発足し、学会になったのが1986年ということで、ちょうど30年だそうです。そしてあの有名な映画、Back to the Futureの公開が1985年であり、映画の中で30年後の未来として2015年が描かれていたなんて、みなさん、ご存じだったでしょうか。
股関節疾患の治療は、長期にわたる経過に基づいて反省と発展が繰り返されてきた分野でもあります。数10年前を振り返り、もし未来を知っていればそのときどのような選択をしたかを考えることで、今後の未来に向けてより良い治療を考えようという、熱意が感じられるプログラムとなっていました。
Akita Hip Research Groupとしてはおそらく過去最多と思われる6演題を発表してまいりました。山田会長の棚形成に関するシンポジウムでのリバース法の発表、非常に多い症例数にもかかわらず、かなり細かい臨床評価をされた田澤先生の人工股関節置換術の発表、A-BONEメンバーでもある加茂先生の人工股関節症例に対する骨粗しょう症治療についての発表、非常に珍しく、治療法をみんなで検討した奥寺先生の症例報告、命にもかかわる合併症でもある静脈血栓塞栓症が起こりやすい症例はどれかという斬新な河野先生の発表、そして、大腿骨近位部骨折に関するAkita分類についても木島が報告してまいりました。秋田だけでなく全国の股関節外科医の明日からの治療に役立つ貴重な情報を会場の先生方に届けることができただけではなく、股関節分野での秋田の活躍をアピールできたと考えています。
股関節学会では毎年、ドクターだけでなく、ナースやフィジカルセラピストの発表の場も設けられており、今年は学会に来られなかった谷貴行先生の手術などをリハビリの観点から解析された秋田赤十字病院リハビリテーション科の齋藤真紀子PTのご発表もございました。
我々の研究成果を発表するだけでなく、全国の先生方のいろいろな考え方に触れることで、秋田の股関節疾患の患者さんにとって有用な情報を少しでも多く取り入れられるようにしっかり勉強してまいりましたので、これを今後の臨床や研究に生かしていきたいと思います。