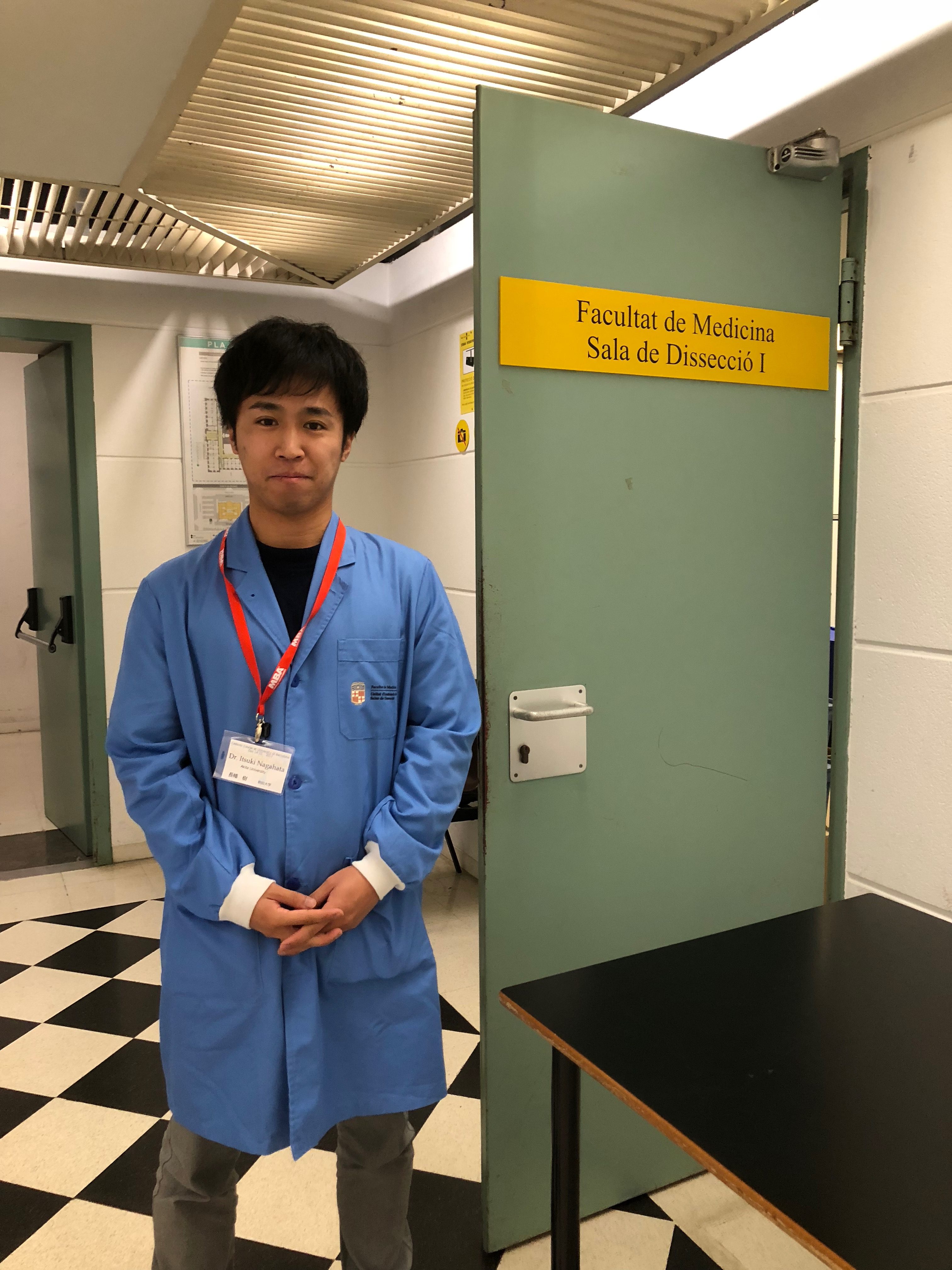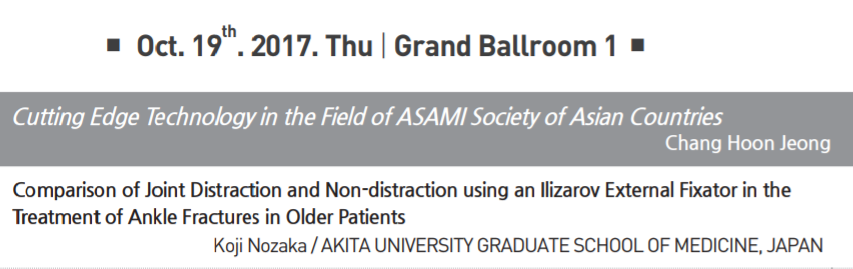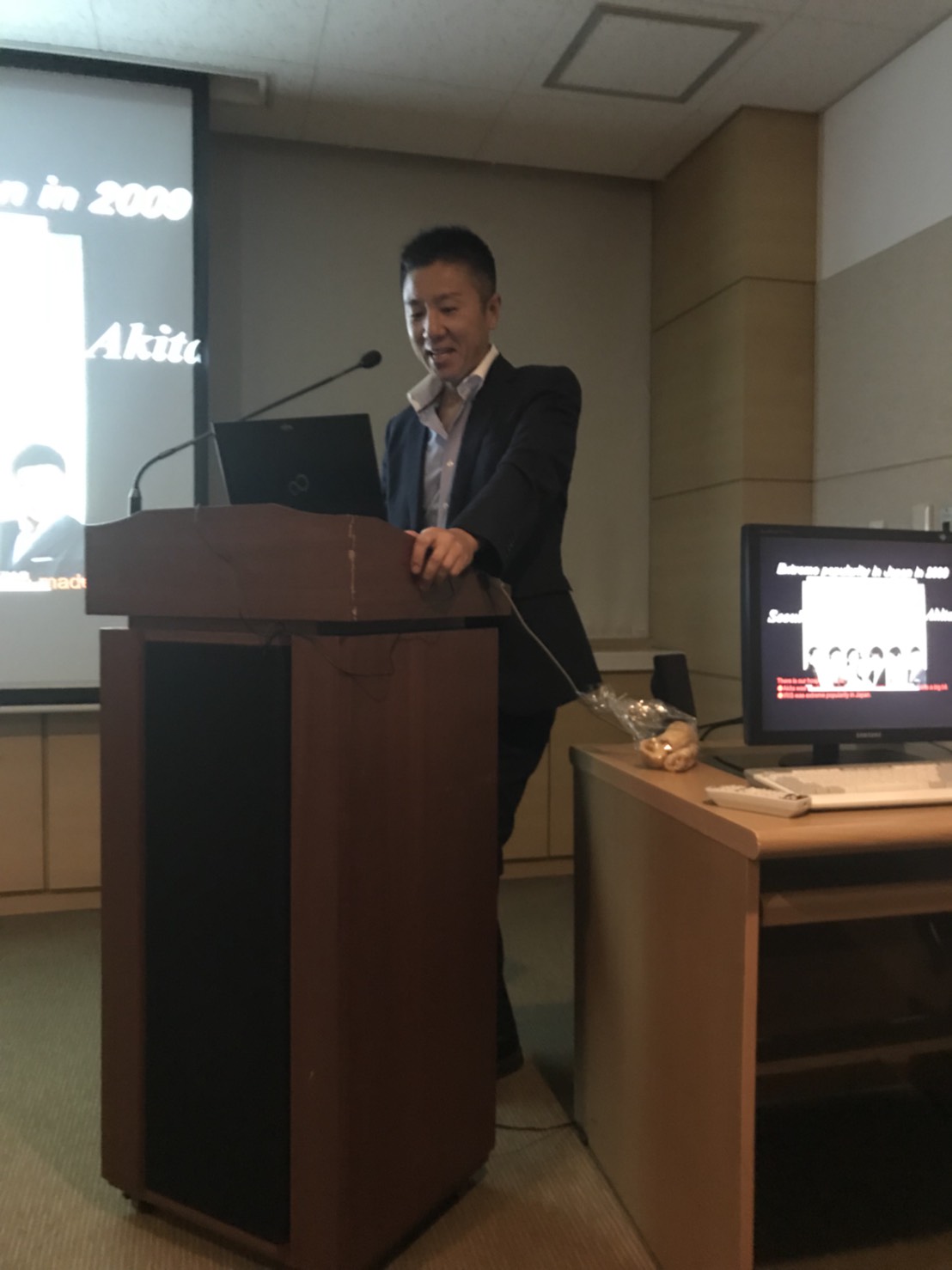秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション科/整形外科の斉藤公男です.2017年9月から島田洋一教授の御高配によりアメリカサンフランシスコ UCSFに留学させて頂いております.これから少しずつ留学中の情報をブログに挙げていきたいと思います.
初回は,セットアップに関してです.サンフランシスコへの留学に関しては非常に役立つ本なども出版されており,そちらに詳しいことが載っていますので,自分で体験した(失敗した)ことを備忘録的に記して起きます.
・とにかくVISAが必要です.VISAが来ないと飛行機も予約できません.自分は始動が遅くて,アメリカ大使館の予約を8月9日にとり,無事に8月16日頃にVISA送付,それから飛行機の予約をしましたが,危ないです.
・VISAを取るためにはDS2019という書類が必要です.
・この書類のために,各種予防接種や,ツ反をしないといけません.
・DS2019は家族の分もしっかり申請しないと,家族のVISAがおりません.自分はこれで遅くなりました.
これ以外にもいろいろ手続きがあるのですが,結局VISAとお金があればなんとかなります.
セットアップのための入国
他大学のサンフランシスコで留学・研究されている先生方にお聞きしたところ,宿は一度場所と現地を見てから決めた方が良いとのことで,9/1〜9/11まで1人で渡航しました.セットアップは北大整形外科 清水智宏先生に多大にお世話になり(居候までさせて頂き),無事にアパートを決めることができました.
日系のリロケーションサービスを利用するのが手っ取り早いらしいのですが,1ヶ月分の家賃を手数料として取られます.自分は清水先生にお手伝い頂き,近くのアパートに直談判でした.結果として,見て決めて正解でした.サンフランシスコは通りが1本違うとガラっと雰囲気が変わるところが多々あります.実際に見てみないと分からないことも多く,特に家族を連れてくる身としては安全は絶対条件でした.今住んでいるところは裏手に警察署があり治安最高に良い場所です.
アパートを借りるために必要だったものは,以下の通りです.
・アメリカの銀行の口座(UNIONBANKなら日本で口座開設できるのですが,間に合いませんでした)⇒借りる予定の部屋を住んでることにして無理矢理口座を開きました…
・携帯電話(日本でSIMカード契約できます.現地の番号が信頼されます)
・パスポート
・DS2019
・現金
・アメリカの雇用主の名前,電話番号(長尾先生ありがとうございました.)
・保証人(いなければ多額のDeposit⇒お金で解決)
・手付金の小切手
☆契約する部屋の1年分の家賃以上の残高証明書(ドル建て,アメリカの銀行のみ):これが一番大変でした…
住居セットアップの合間に,サンフランシスコ周辺で医師として勤務されているAko Walter先生(湊正策会長の愛娘,湊貴至先生の妹,齊藤英知先生の同級生)に山火事に見舞われる前のナパ・ソノマ周辺のワイナリー巡りに誘って頂き大変貴重な経験をさせて頂きました.この場を借りて御礼申し上げます.
一時帰国.時差ボケ全開で青森の実家行ったり,仙台行ったり,大学病院行ったりであっという間に家族を連れて再び米国へ,途中何故か同期の奥寺先生に会って家族との集合写真撮ってもらったり…
つづく

ダウンタウン

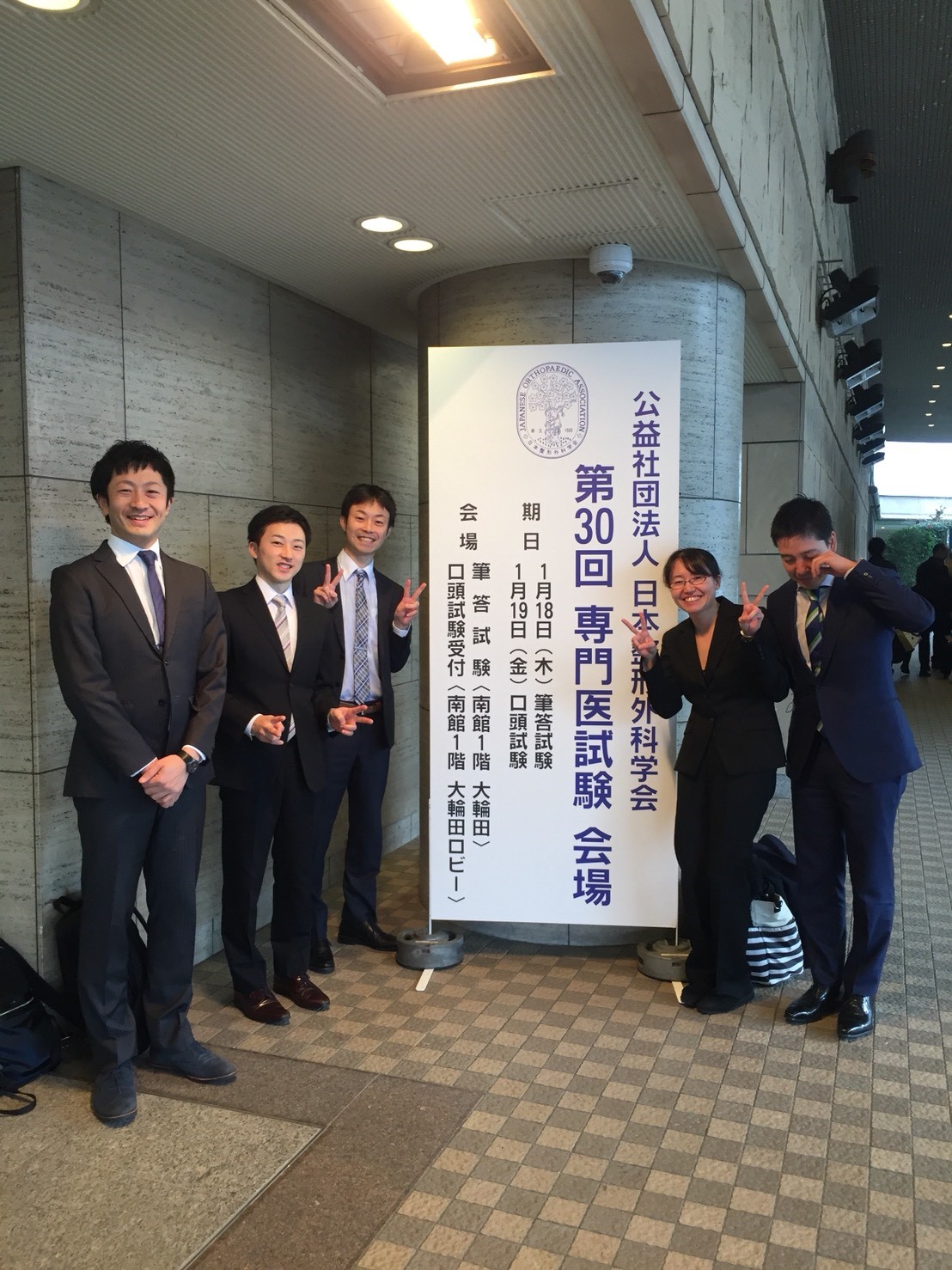




 今回は、数ある整形外科関連学会の中でも会員数の多い日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下JOSKAS)で始まった関節鏡技術認定制度(膝関節)について解説します。関節鏡手術は、日本で開発された歴史があり、非常に低侵襲であり、多くの関節で普及し、実施されてきました。しかし、特殊な器具を用いて行う手術であり、高度な技術が要求されます。このJOSKASの関節鏡技術認定制度は、共通の基準にしたがって鏡視下手術に携わる医師の技量を評価し、一定の高い基準を満たした者を認定するもので、これにより本邦における鏡視下手術の健全な普及と進歩を促し、延いては国民の健康や福祉に貢献することを目的とし制度化されました。認定の要件は、
今回は、数ある整形外科関連学会の中でも会員数の多い日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下JOSKAS)で始まった関節鏡技術認定制度(膝関節)について解説します。関節鏡手術は、日本で開発された歴史があり、非常に低侵襲であり、多くの関節で普及し、実施されてきました。しかし、特殊な器具を用いて行う手術であり、高度な技術が要求されます。このJOSKASの関節鏡技術認定制度は、共通の基準にしたがって鏡視下手術に携わる医師の技量を評価し、一定の高い基準を満たした者を認定するもので、これにより本邦における鏡視下手術の健全な普及と進歩を促し、延いては国民の健康や福祉に貢献することを目的とし制度化されました。認定の要件は、