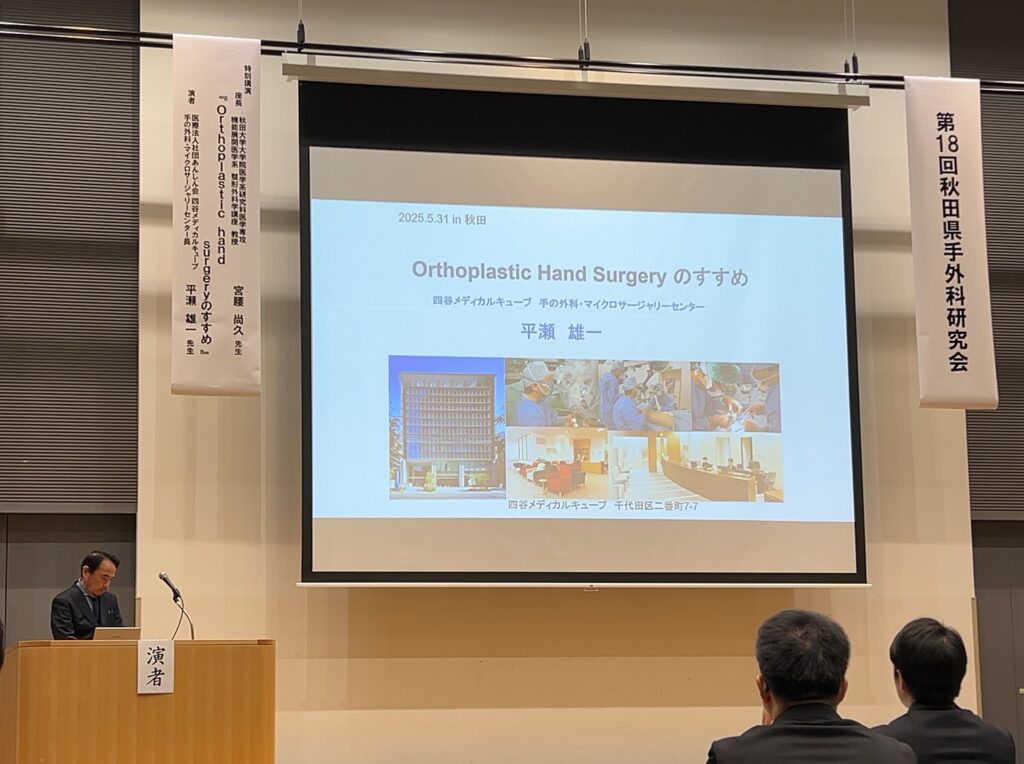2025年5月31日(土)に第18回秋田県手外科研究会が開催されました。秋田さとみ温泉にて例年開かれていたこの会ですが、今年は秋田拠点センターALVEにて執り行われました。同門の先生方だけでなくハンドセラピストの方々にも多く足を運んでいただき、広い会場が埋まるほどの盛況でした。
会に先立ち行われた幹事会では、近年AHG/AFTTGとしての学会活動や論文執筆が増えてきていることが取り上げられ、若手の自分もその一員となるよう頑張らねばと感じました。
一般演題では白幡毅士会長の座長のもと、5演題の発表がありどれも活発な議論がなされました。齋藤先生の肘頭骨折TBWのバックアウトについての検討では、リングピンを使用すべきとの御意見も確かに道理にかなうものと存じますが、安価でどんな病院にも必ず置いてあるK-wireを使用し、いかなる手術法でどんな工夫をするとBack outを防ぐことに繋がるのかという検討内容も非常に興味深いと自身は感じました。加賀先生の陳旧性スワンネック指のお話では、普段外来でよく見る掌側板損傷の成れの果てにこのような病態に発展する場合もあるのだと実感しました。
ミニレクチャーでは、秋田赤十字病院の湯本聡先生より「四肢主要血管損傷の治療経験」として、現在までに経験してこられた四肢重度外傷の症例の数々や初期治療医にどういったことが求められるかについて熱くご講演頂きました。本会の幹事会では湯本先生より退会の御挨拶がございましたが、湯本先生は本当に長い間ずっと秋田県の重症外傷治療を支えてこられ、今現在もなお第一線で御活躍されております。湯本先生と一緒に勤務し外傷治療を学んできた若手整形外科医は多いですし、これからも我々に引き続き御指導を頂きたいと強く思っております。
特別講演では、四谷メディカルキューブ 手の外科・マイクロサージャリーセンター長 平瀬雄一先生に「Orthoplastic hand surgeryのすすめ」と題してご講演いただきました。Orthoplasticとは、おもに(重度)四肢外傷に対して、皮膚軟部組織再建と骨折治療・骨関節再建の両方を行う外科分野のことを指します。平瀬先生はそこへ到達する道を登山に例えられ、Orthoplastic山に登るにはOrthopedic山からもPlastic山からも登れるが、お互いの分野をよく理解することが大事だと仰いました。 ご存じの方も多いと思いますが、平瀬先生はかの有名な著書「やさしい皮弁」「やさしいマイクロサージャリー」の著者であります。やさしい皮弁の最初のページには、聞くだけでなく、見て行動してはじめて理解ができるのだという意の孔子の言葉が書かれています。その言葉の通り、講演のスライドには実際の症例写真や手術動画が非常に多く盛り込まれており、神業の数々にただただ圧倒されました。個人的には、wrap-around flapの手技で1趾だけでなく2趾からも連続したflapをあげ1本の指を再建する手技や、爪床移植により爪の一つまでこだわって再建するところに、flap surgeonならびにOrthoplastic surgeonとしての流儀や、患者様への思いを感じました。
講師を囲む会では、秋田の日本酒を飲みながら、AHGの先生方が皆こぞって平瀬先生に質問をし、本会では聞ききれなかったことを余すことなく教えて頂きました。平瀬先生本当にありがとうございました。
今回の研究会で学んだPlastic surgeryの考え方、tipsを活かして、AHG/AFTTGの一員としてこれからも頑張っていきたいと思います。本会がご参加いただいた先生方の日常診療の一助となりましたら幸いです。